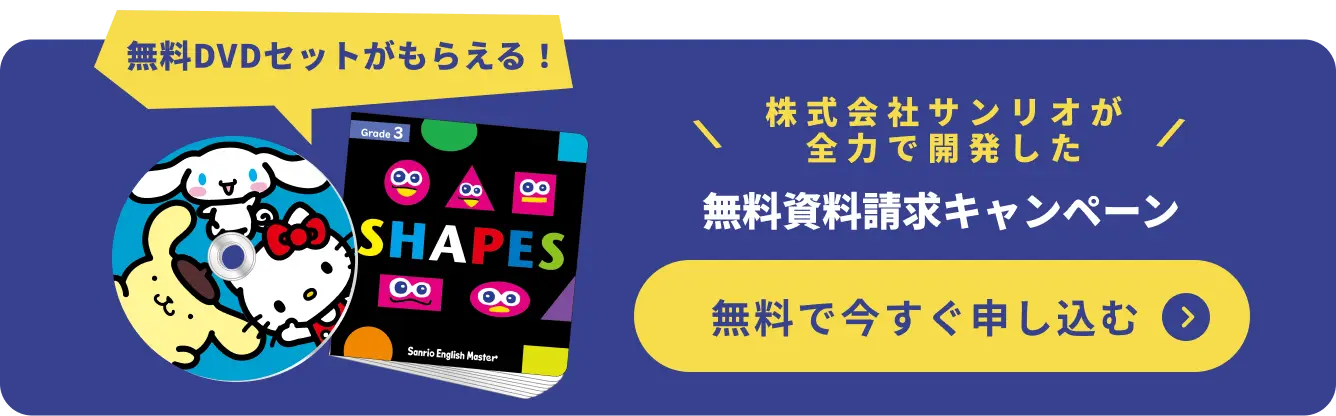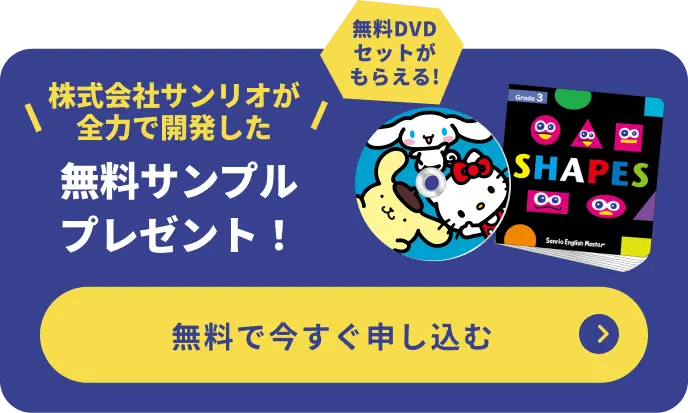【年齢別】理想的な子供の睡眠時間は?寝つきをよくする効果的な方法もご紹介

一般的に推奨されている子供の睡眠時間は年齢によってさまざまです。
この記事では、推奨される子供の睡眠時間を年齢別にクローズアップします。また、睡眠不足によるデメリットや早寝早起きのメリット、お子さまの寝つきをよくする方法も紹介します。お子さまの睡眠について理解を深め、健やかな成長につなげましょう。
目次
日本人の睡眠事情
睡眠時間の長さは国によってさまざまです。そこで、日本人全体の睡眠事情について解説します。
世界的に見て日本人の睡眠時間は短い
経済協力開発機構(OECD)は、2021年に世界各国の平均睡眠時間に関するデータを発表しました。発表されたデータによると、先進国を中心に世界33か国を対象に調査した結果、日本人の睡眠時間は短い傾向にあることが分かっています。
データで発表された日本人の平均睡眠時間は、1日あたり7時間22分です。各国の平均睡眠時間は8時間28分なのに対して、日本人は睡眠時間が1時間以上も短いという結果になりました。
※参考:Gender Data Portal | World Bank Gender Data Portal
日本人の子供の睡眠時間も短い
2021年に株式会社ブレインスリープが実施した調査によると、日本の3歳~9歳の子供の睡眠時間は、全年齢で推奨される時間に達していないことが明らかになりました。特に、年齢が上がるにつれて睡眠時間が短くなる傾向があり、小学生になるとさらに不足が顕著になります。
さらに、この調査では「日本の子供の睡眠時間は世界で最も短い」という事実を詳しく知っている人はわずか5%にとどまり、多くの人がこの問題を認識していないことも分かりました。実際、68.7%の人がその事実すら知らなかったという結果が出ています。
※参考:睡眠偏差値 調査結果報告 KIDS 2021 | BRAIN SLEEP OFFICIAL SITE
夜型生活になり、睡眠不足の子供が増加
インターネットやスマートフォンの普及、グローバル化の進展により、社会全体が24時間型になりつつあります。人によっては生活が夜型化し、大人だけでなく子供たちも習い事などで生活が夜型化しているケースが少なくありません。
公益社団法人日本小児保健協会の調査結果によると、夜10時以降に就寝する子供の割合は、1歳6か月・2歳・3歳で半数を超えたと判明しました。このように子供も夜型生活となっているため、睡眠時間が減少しているとされています。
※参考:平成22年度幼児健康度調査報告|公益社団法人 日本小児保健協会
厚生労働省が公表した睡眠12箇条とは
厚生労働省では指針は睡眠の充実度を高めることを目的にした「健康づくりのための睡眠指針2014」を提示しています。この指針では、適度な運動や朝食の重要性や、年齢や季節に応じた睡眠などが睡眠12箇条に分けて解説しています。
なお、同指針は2023年に改訂が行われ、年代別にまとめられています。
睡眠・休養の推奨事項と、睡眠・休養に係る参考情報など、改訂版の睡眠指針においては、子供に推奨睡眠時間を設定し、夜更かしや寝坊に対する注意喚起もなされています。
※参考:健康づくりのための睡眠ガイド 2023 (案)|厚生労働省
【年齢別】子供の推奨睡眠時間
続いて、厚生労働省およびアメリカの国立睡眠財団による情報をもとに、子供の推奨睡眠時間について解説します。
※参考:健康づくりのための睡眠ガイド 2023 (案)|厚生労働省
※参考:How Much Sleep Do You Really Need?|National Sleep Foundation
生後3か月まで:1日14~17時間
アメリカの国立睡眠財団が推奨する生後3か月までの睡眠時間は、1日14~17時間です。生後間もない赤ちゃんは眠るのが仕事といっても過言ではありません。生後3か月までの赤ちゃんは、1日のほとんどを寝て過ごします。しかし、長時間眠ったままというわけではありません。哺乳や排せつのために3~4時間ごとに目覚めます。
4~11か月:1日12~15時間
アメリカの国立睡眠財団が推奨する生後4~11か月の睡眠時間は、1日12~15時間です。睡眠時間は先述した新生児の頃よりも減ってきますが、それでも1日の半分以上は寝て過ごします。ただし、新生児の頃と比べると昼間に起きていられる時間が長くなるため、睡眠時間が夜に集中してくるようになります。
1~2歳:1日11~14時間
1~2歳における推奨睡眠時間は、1日11~14時間です。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、アメリカの国立睡眠財団でも1日11~14時間が推奨されています。成長して子供が歩けるようになると、外に出かける機会が増えるため、生活リズムが整い、夜に寝る習慣がついてきます。
3~5歳:1日10~13時間
3~5歳の推奨睡眠時間は、1日10~13時間です。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」でも、アメリカの国立睡眠財団でも1日10~13時間と定められています。なお、保育園では昼寝の時間が設けられていますが、年齢が上がると昼寝しない子供も出てきます。
6~13歳:1日9~12時間
小学校では昼寝をするための時間が設けられていません。さらに、小学校に入ると習い事などで帰宅時間が遅くなる子供も増えるため、睡眠時間が減る傾向があります。しかし、健康的な生活のためには1日9~13時間は睡眠時間を確保したいところです。
睡眠不足によるデメリット
睡眠時間が十分に確保できていない状態だと、以下のようなデメリットがあるとされています。
成長ホルモンの分泌に影響が及ぶ
子供の健康と発達を助けるのは、成長ホルモンです。身長を伸ばしたり、筋肉量を増やしたり、免疫力を高めたりするためには、成長ホルモンが欠かせません。
成長ホルモンは体内リズムに合わせて分泌される仕組みで、体内リズムを整えるために睡眠は重要な要素です。しかし、睡眠不足によって体内リズムが崩れると、成長ホルモンの分泌が不十分となってしまうため、子供の健康や発達に影響を及ぼすとされています。
集中力・意欲の低下
睡眠不足は集中力や意欲の低下にもつながり、日中の活動に影響を及ぼすといわれています。睡眠は、疲労回復のために欠かせません。しかし、睡眠時間が不足していると脳と身体を十分休ませられず、疲れがとれずに1日を過ごすこととなります。
睡眠が不足している状態だと、日中に眠気が強く出てぼーっとしてしまう可能性があります。注意力が散漫となり、ケガをしてしまうリスクも高まります。
体内時計が整わない
人間の睡眠と覚醒のサイクルは、「体内時計」と呼ばれるリズムから調整されます。体内時計が正常に働くことで、朝は自然と目が覚め、夜になると眠くなるという健康的なリズムが維持されます。そのため、体内時計を整えることは、規則正しい生活を送るために欠かせない重要なポイントです。
しかし、睡眠不足や不規則な生活が続くと、体内時計のバランスが崩れ、朝起きるのがつらくなったり、昼間に強い眠気を感じたりすることがあります。さらに、夜になっても寝つけず、睡眠リズムが乱れる悪循環に陥ることも少なくありません。
子供が早寝・早起きするメリット
子供が早寝・早起きする最大のメリットは、生活リズムが整い、成長を促しやすくなることです。規則正しい睡眠習慣が身につくと、朝はすっきりと目覚め、夜には自然と眠くなる健康的なサイクルを維持しやすくなります。
もともと人間は昼行性の動物であり、昼に活動して夜に休息をとることが、心と体の発達に適しているとされています。特に子供の場合、夜の睡眠中に成長ホルモンが活発に分泌されるため、十分な睡眠を確保することが成長に欠かせません。このように、早寝・早起きが推奨されるのには、生物学的な根拠があります。
子供の寝つきをスムーズにするには?
「子供の寝つきが悪い」と悩む方は少なくありません。ここでは、スムーズに眠れるようにするためのポイントを紹介します。
就寝1~2時間前までには入浴する
入浴は、就寝1~2時間前までに済ませましょう。体温が下がると自然に眠気が訪れるため、このタイミングで入浴するとスムーズに寝つきやすくなります。ただし、温度設定には注意が必要です。42℃以上のお湯は交感神経を活発化させてしまうため、38~40℃の温度にしましょう。
寝る前に電子機器を使用させない
寝る前のスマートフォンやタブレット、パソコンの使用は控えましょう。これらの画面から発せられる光を浴びると、脳が昼間と錯覚し、眠気を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されます。その結果、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする可能性があります。「就寝◯時間前まで」など、ルールを決めて使用時間をコントロールすることが大切です。
部屋を暗くする
電子機器の使用を控えるだけでなく、部屋の明かりを暗くすることも大切です。夜に強い光を浴びると、眠気を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑えられ、寝つきが悪くなる原因になります。そのため、低色温度・低照度の照明に切り替えると、自然な眠りに誘われやすくなります。夕方以降は、次第に明かりを暗めに調整すると効果的です。
また、部屋を暗くして天井に映せる絵本プロジェクターなどを活用すると、お子さまが布団に入るきっかけを作りやすくなるでしょう。
朝日をしっかりと浴びる
就寝時の工夫だけでなく、朝にカーテンを開けて太陽光を浴びることも大切です。朝日を浴びると体内時計がリセットされ、自然な目覚めを促します。体内時計が整うことで、夜は自然と眠気が訪れ、スムーズに寝つきやすくなります。
また、起床後1時間以内に朝日を浴びると、体温や代謝を活発にする「コルチゾール」の分泌が促され、日中の活動がスムーズになります。朝の光をしっかり取り入れ、心地よい1日をスタートさせましょう。
早起きの習慣をつけさせる
早く起きられるようになると、自然と早寝の習慣がつきます。そのため、まずはお子さまが早寝できるよう決まった時間に起こすことが重要です。最初はなかなか起きられなくても、カーテンを開けて朝日を入れたり、リビングに移動させたりするなどの工夫により朝型の体内リズムになります。無理のない範囲で、少しずつ早起きの習慣を身につけさせましょう。
朝ごはんを食べる
朝ごはんを食べると体内時計がリセットされ、生活リズムが整いやすくなります。朝日を浴びるのと合わせると、さらに効果的です。また、朝ごはんは1日のエネルギー源となり、体温が上がって脳も活性化します。日中を元気に過ごせるため、夜には自然と眠気が訪れ、寝つきがよくなります。
昼間にたっぷり行動する
日中にしっかり活動することで、夜の寝つきがよくなり、深い眠りにつながります。勉強や運動などで体を動かし、適度に疲れることが大切です。一方で、昼間に長時間眠る習慣が続くと、体内時計が乱れ、夜に眠れなくなる原因になります。日中はできるだけ活動的に過ごし、自然な眠気を引き出しましょう。
寝つきが悪い子供は睡眠障害の場合も?
生活習慣を正してもお子さまの寝つきがよくならない場合は、睡眠障害を患っている可能性もあります。睡眠障害とは、睡眠に何かしらの問題が生じている状態のことです。不眠や就寝・起床時間が遅くなる睡眠相後退症候群、日中に異常な眠気に襲われるナルコレプシーなども、睡眠障害として挙げられます。
さまざまな対策を行っても寝つきがよくならず不安を抱えているようであれば、医療機関に相談してみましょう。
子供の成長には教材選びも重要
お子さまの成長には十分な睡眠時間を確保するだけでなく、適した教材を利用することも重要です。
生活習慣だけでなく、教材も大切な存在
この記事でご紹介したように、推奨される睡眠時間を習慣づければ集中力が向上するため、教材を使った学習よりも効果的にできるでしょう。しかし、お子さま向けの教材といっても種類はさまざまです。教材選びの際には、お子さまが楽しめるエンタメ要素があるか、無料トライアルサービスがあるかなどをチェックする必要があります。
英語教材はSanrio English Masterがおすすめ
お子さま向けの英語教材を使うなら、Sanrio English Masterがおすすめです。Sanrio English Masterは、幼児・小学生向けの英語のDVD教材です。0歳から8歳まで学べる充実したカリキュラムで、楽しく遊びながら英語が身につく内容になっています。
Sanrio English Masterには、お子さまの興味・関心を引き出すキャラクターが登場するほか、学習プログラムに連動したおもちゃや絵本を展開しているのも特徴的です。無料モニターキャンペーンも開催しているため、気軽に試すことができます。
また、Sanrio English Masterでは、お子さまが心地よく眠れるように、Dream Switchという絵本プロジェクターも含まれています。Dream Switchは、壁や天井に映像を映して、寝る前の読み聞かせをゆったりと楽しむことができる絵本プロジェクターです。
ハローキティやシナモロール、ポムポムプリンなど、お子さまが大好きなサンリオキャラクターズの絵本が15タイトル、そして童謡も16曲収録されています。充実した内容のため、夜も元気なお子さまでも、自ら進んで布団に入りたがるでしょう。
※『Dream Switch』は株式会社セガ フェイブの登録商標です。
まとめ
十分な睡眠は、お子さまの成長に欠かせない重要な要素です。お子さまの寝つきが悪い場合には、就寝1~2時間前までに入浴を済ませたり、朝日をしっかり浴びたりといった習慣を心掛けましょう。
なお、教材選びも大切なポイントとなります。記事内で紹介した英語教材のSanrio English Masterは、楽しく遊びながら英語が身につく内容となっているため、お子さま向けの英語教材を探している方におすすめです。Sanrio English Masterでは、無料サンプルを配布しているほか、無料の教材体験キャンペーンも開催しています。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。