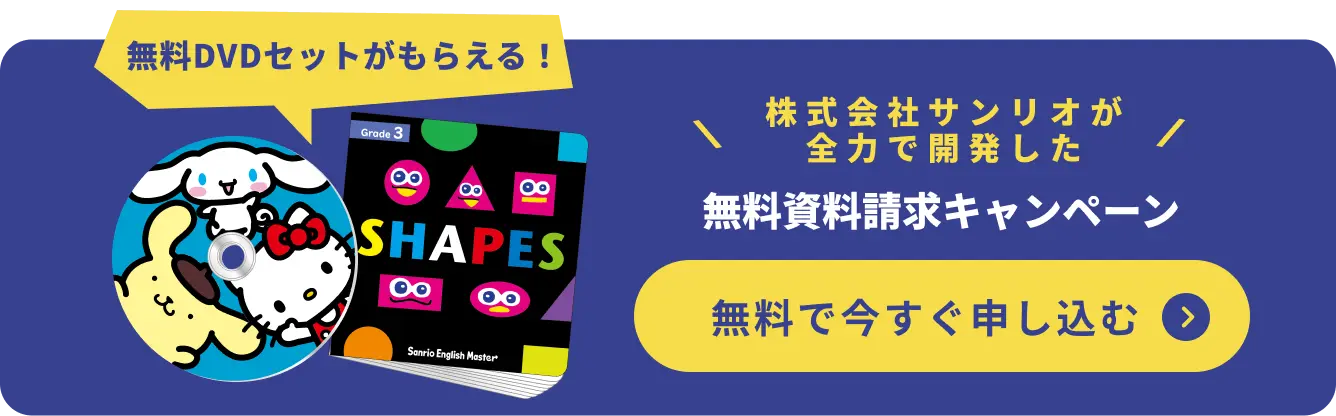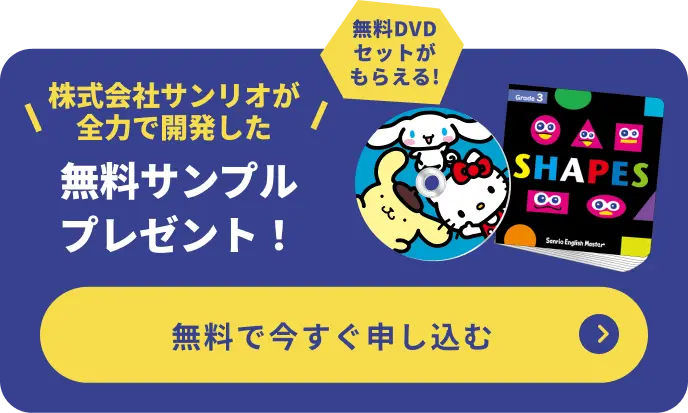イヤイヤ期にはどう対応すればいい?正しい対処法、避けるべき接し方を解説

子育てでも苦労が多いといわれる期間がイヤイヤ期です。イヤイヤ期の対応に悩むおうちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、イヤイヤ期とは何なのか、イヤイヤ期のお子さまへの対応方法などを解説します。また、イヤイヤ期に避けるべき接し方や、イヤイヤ期で疲れてしまったときの対処法なども解説するため、ぜひ参考にしてください。
子どものイヤイヤ期とは?
イヤイヤ期とは、子どもが何に対しても「イヤ」と主張する時期を指します。一般的にイヤイヤ期は、2歳前後で起こりやすいといわれています。イヤイヤ期には、何をしてもイヤイヤと泣いたり、癇癪を起こしたりする傾向にあるため、保護者もどうしたらよいかわからず、子育てにおいて苦労が多い時期だといえるでしょう。
イヤイヤ期はずっと続くわけではありません。時間とともに落ち着く傾向にあるため、お子さまが落ち着くまで見守ることが大切です。
イヤイヤ期の原因
イヤイヤ期はなぜ起こるのでしょうか。ここでは、イヤイヤ期が起こる原因を詳しく解説します。
自立心が芽生えたため
成長するにしたがって、子どもは自分でできることが増えていきます。また、自分で着替えや片付け、食事などに挑戦することによって、好奇心を満たすという側面もあります。身の回りのことを自分でやりたい、何にでも挑戦してみたいという気持ちが強くなり、保護者の手伝いを嫌がるようになることで、イヤイヤ期が起こるようです。
できないことが不満に感じるため
2歳前後の子どもは自分でやってみたいという思いが強く、挑戦すること自体が喜びだったり、好奇心が満たされたりします。しかし、まだうまくやり遂げられないことも多くあります。うまくできないことでストレスや不満を感じることもあるでしょう。自分でやりたいという気持ちから、保護者の手伝いを嫌がって対応が難しいこともあります。
感情表現が未発達のため
2歳前後の子どもは、言語能力やコミュニケーション能力などが未発達です。そのため、感情をうまく表現できず、癇癪を起こすことがあります。また、「眠い」「疲れた」などの感情を自覚できずに、不快感に対処できないこともあります。感情をコントロールする前頭前野も未発達なため、イヤな気持ちを我慢できないケースも多いようです。
周囲の気を引きたいため
周囲の気を引きたいと思って、癇癪を起こすこともあります。乳児に比べて幼児は自分でできることも増えるため、大人の世話になる時間が減ります。「もっと甘えたい」「構ってほしい」という気持ちをうまく伝えられず、わざと大人を困らせて気を引こうとするケースもあるようです。
イヤイヤ期の避けるべき対応
イヤイヤ期の子どもの特性上、つい大きな声で叱ってしまったり、強く注意したりする保護者も少なくありません。ここでは、イヤイヤ期の子どもに対して避けるべき対応を解説します。
感情的に叱ってしまう
感情的に叱るのは禁物です。感情的に叱ってしまうと子どもが恐怖心を感じてしまい、子どもとの信頼関係が崩れてしまう恐れがあります。子どもが委縮して伸び伸びと過ごせなくなるケースもあるため、注意しましょう。また、感情的に叱ったり怒鳴ったりすると、叱った側も自己嫌悪に陥りやすくなります。
「ダメ」と押さえつけてしまう
子どもの要望や要求をすべて叶えることは難しいことがあります。しかし、何でも「ダメ」と押さえつけてしまうのはやめましょう。子どもの意見や要望を聞かずに、すべて「ダメ!」と押さえつけてしまうと、子どもの意欲が低下しかねません。また、何をしても「ダメ」といわれることで、自己主張がうまくできなくなる可能性があります。
分かりにくい言葉で注意する
2歳前後の子どもは、曖昧な表現や難しい表現での注意は伝わりにくい傾向があります。例えば、「いい加減にしなさい」「どうしてそういうことをするの?」などと言っても、なかなか伝わりません。そのため、「おもちゃを投げると壊れるから投げないでね」「走ると危ないから歩こうね」など、具体的に話すように心がけましょう。
お子さまから離れてしまう
子どもの癇癪にイライラして、落ち着くまで離れたくなる場合もあるかもしれません。しかし、そこで離れてしまうと子どもは見捨てられたと感じることがあります。不安や寂しさを感じてしまわないよう、子どもが落ち着くまで側にいるようにしましょう。目が届く範囲で静かに見守ったり、話を聞いたりすることが大切です。
脅し・命令・交換条件を出す
「静かにしないとおばけが出るよ」などと、子どもが恐怖を感じる脅しは避けましょう。また、「静かにしなさい!」などの命令するような口調もNGです。「おもちゃを買ってあげるから」などの交換条件も提示しないようにします。
これらの対応では、子どもが「何がダメなのか」「ダメな理由」を学べない可能性があります。結果として同じことを繰り返すことにつながるため、できるだけ理性的かつ前向きな言葉を心がけましょう。
イヤイヤ期の適切な対応
イヤイヤ期の対応で困っているおうちの方も多いでしょう。ここでは、イヤイヤ期の適切な対応を解説します。
子どもの気持ちに寄り添う
まずは、子どもの気持ちに共感を示しましょう。「イヤなんだね」と共感してあげることで、落ち着きを取り戻すケースもあります。共感を示されることで、自分の気持ちを分かってくれていると子どもは安心できます。お子さまのイヤな理由やしたいことを聞き、おうちの方が代替案を出すことで、納得したり気持ちが切り替わったりすることもあるようです。
さりげなくサポートをする
子どもが自分で何かをしようとすると時間がかかります。しかし、大人が手伝ってしまうと自己肯定感が育まれません。また、手を出されることで余計に癇癪がひどくなることもあるでしょう。そのため、さりげなくサポートすることが大切です。例えば、ボタンを半分お子さまに留めてもらい、残り半分をおうちの方が留めるなどします。
ワンクッション置いて接する
子どもが何かに熱中しているときは、気持ちの切り替えが難しいです。そのため、別の行動を提案しても拒絶されやすいでしょう。そのため、あらかじめの声掛けなどでワンクッション置くことがポイントです。例えば、「そのお絵描きが終わったら、お片付けしてご飯にしようね」などと声掛けをします。
お子さまを見守る
状況によっては、お子さまを静かに見守ることも重要です。子どもは自分のペースで物事を進められなかったり、無理に中断させられたりする不満から、イヤイヤを発している場合もあります。お子さまのイヤイヤを出し切るまで待ってみましょう。また、「自分が落ち着くまで待ってくれた」という経験が、お子さまに安心感を与えることもあります。
具体的に分かるルールを決める
子どもには曖昧な表現では伝わりません。例えば、「あと少し」などでは伝わらないでしょう。そのため、子どもが分かるように具体的なルールを決めることが重要です。「時計の長い針がここに来たら、お片付けをしようね」「お菓子は1つだけね」というように、おうちの方が具体的なルールを設けることで、お子さまが何をすればよいのか理解しやすくなります。
気持ちを逸らす働きかけをする
「おうちに帰ったらおやつを食べようね」というように、この先にある楽しいことを伝えて気持ちの切り替えを促します。こだわっているものから気持ちを逸らすことで、落ち着く可能性もあります。ただし、あくまでもお子さまを冷静にさせることが目的です。ダメなことは、後からしっかり伝えるようにしましょう。
イヤイヤ期で疲れてしまった場合の対策
イヤイヤ期の子どもの対応に疲弊してしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。ここでは、イヤイヤ期に疲れた場合の対策を解説します。
時間・スケジュールに余裕を持たせる
スケジュールに余裕を持たせましょう。時間やスケジュールに追われているとストレスが溜まってしまい、「なぜ言うことを聞かないのか」とイライラしてしまいます。そのため、できるだけ余裕を持って行動するように習慣づけましょう。時間に余裕があれば、子どもを急かす場面も減らせます。
無理に干渉しない
イヤイヤ期の子どもには干渉し過ぎないようにしましょう。むやみに手伝ったりせずに見守る姿勢を取ります。心身ともに疲れてしまった場合は、少し距離を取ることも選択肢のひとつです。ただし、前述したように、離れると子どもは見捨てられたと感じる可能性があるため、部屋や家からは出ずに、大人のぬくもりが感じられる距離を保ちましょう。
イヤイヤ期への具体的な対応例
イヤイヤ期には、ご飯を食べなかったり寝るのを嫌がったりすることもあります。ここでは、イヤイヤ期への具体的な対応例を解説します。
ご飯を食べない・ご飯で遊んでしまう
ご飯を食べない場合には、無理に食べさせようとしないほうがよいでしょう。無理に食べさせると余計に機嫌が悪くなることもあります。ご飯で遊んでしまう場合は、その段階で食事を切り上げます。栄養補給のために食事をしっかり取らせることも大切ですが、食事は決められた時間に食べる必要があると学ばせることも大切です。
寝ずに遊びたがる
子どもは体力が余っていると、寝ずに遊びたがる場合があります。その場合は、「今は寝る時間だから寝ようね。起きたら遊ぼう」と言って、電気を消しましょう。この際、寝る前の約束は必ず叶えるようにすると、寝ることに納得しやすくなります。約束を守ることで、自分の気持ちを受け入れてもらえたという納得感も生まれます。
まとめ
イヤイヤ期とは、2歳前後に起こる何に対してもイヤイヤと主張する時期です。自立心の芽生えや感情表現がうまくできないことなどから、癇癪を起こしてしまいます。イヤイヤ期には、子どもの気持ちに寄り添って見守ることや、具体的なルールを決めることなどを心がけましょう。
Sanrio English Masterは、エンターテインメント性の高い英語教材です。メインキャラクターのエディはお子さまと同じくらいの年齢で、イヤイヤ期を経て少しずつ成長します。絵本のなかには食育をテーマにしたものがあり、エディが苦手な野菜を自分で育てることで、食べ物の大切さを学べる仕様です。
イヤイヤ期のお子さまと同様に初めは嫌がっていても、背景や意図を理解することにより成長していける内容も取り入れています。無料DVDセットなら、この食育絵本が全編無料でついてきます。イヤイヤ期のお子さまの英語教育や食育などをお考えなら、ぜひ一度お試しください。