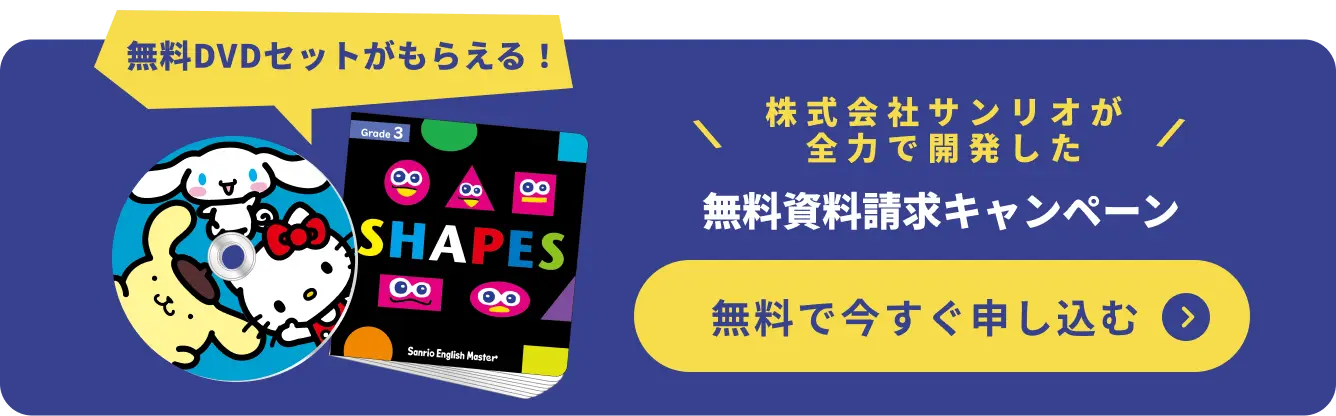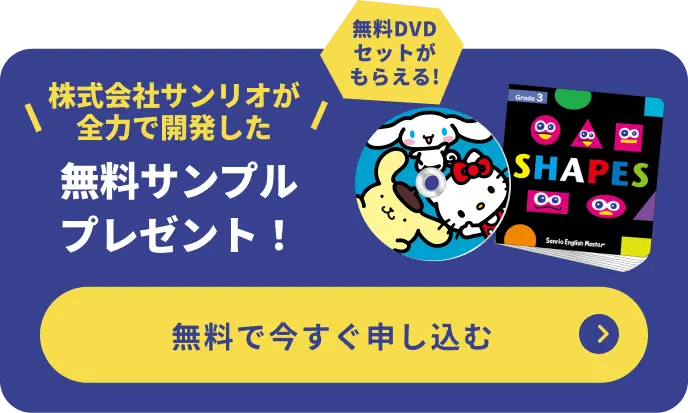子どもの非認知能力を鍛える遊びとは|具体例や実践する際のポイントも解説

子どもに幼児教育を始めたいと検討している際、子どもの非認知能力を高める重要性を耳にすることがあるでしょう。しかし、非認知能力とはどのようなものか、詳しく知らない方も少なくないはずです。
そこで本記事では、非認知能力について情報収集している方に向け、非認知能力を鍛えるメリットや遊びの具体例を解説します。非認知能力を鍛える際のポイントや、その注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
非認知能力に関する基礎知識
まずは、非認知能力とはどのようなものなのかを詳しく解説します。
非認知能力とは
非認知能力は、人の内面的な能力のことで、人格形成に関わるものとされています。また、非認知能力は、勉強やビジネスの場面にも影響するとされています。
非認知能力と認知能力の違いや関係性
認知能力は、知識や技能、思考力などを指しているもので、数値化が可能な能力です。例えば、テストの点数などで表せるものが認知能力です。
一方で非認知能力は、認知能力に該当しない能力全般を指しており、自分のなかにある内面的なもので、数値化が難しいとされています。認知能力と非認知能力は、どちらも子どもの成長には不可欠なものであり、相互に作用して育まれます。
主な非認知能力の種類
自分の内面にある能力である非認知能力には、いくつかの種類があります。
自身を信じ、愛する力
自身を信じ、愛する力とは、ありのままの自分を愛し、受け入れて、肯定する力のことです。
自分を肯定できると、失敗したときに自分を責めすぎず、失敗を次に活かせるようになります。
自身と向き合う力
自身と向き合う力とは、自身の内面と向き合い、自身の精神状態を確認したり調整したりする力です。これには、具体的に次のような力があります。
- 自制心:感情任せにならず、自分をコントロールできる力
- 忍耐力:物事を粘り強くやり抜く力
- 主体性:自分の意志で行動し、遂行する力
- メタ認知:知覚、記憶、思考などの自分の考えや感情を客観的に捉えて言語化する力
- ストレス管理能力:自身のストレスを理解し、うまく対応する力
- レジリエンス:困難な状況になっても気持ちを切り替えて、本来の力を発揮する力
自身を高める力
自身を高める力とは、自身を変革し成長させる力です。これには、具体的に次のような力があります。
- 内発的動機付け:自身の気持ちを動機としてモチベーションを引き出す力
- 自己肯定感:ありのままの自分を認める力
- 自己効力感:やるべきことをやり遂げられると自分に自信を持つ力
- 意欲:集中力を持って取り組めるやる気
- 向上心:新しいことに挑戦する力
他者とつながる力
他者とつながる力とは、他者と協調、協働するための力です。これは、自身と向き合う力や自身を高める力などの対自的な力ではなく、対他的な力を指します。具体的には次のような力があります。
- リーダーシップ:仲間に気を配ったり、フォローしたりしながら集団をまとめ上げる力
- コミュニケーション能力:言葉だけでなく、身振り手振りのような動作や表情などを意識しながら周りの人と意思疎通を図る力
- 協調性:周囲を理解し、思いやりを持ってともに行動できる力
- 共感性:相手の言動だけでなく、行動などからも感情や意図を汲み取る力
子どもの非認知能力を高めるメリット
子どもの非認知能力を高めることには、多くのメリットがあります。主な4つのメリットを解説します。
学習効率が上がる
認知能力と非認知能力は相互関係にあるため、非認知能力を鍛えると、認知能力も向上します。認知能力が向上すれば、思考力が高まり、知識も深められるため、結果として学習効率が上がり、学力の向上にもつながります。
また、非認知能力を鍛える過程で、自立心も養われるため、勉強に積極的に取り組むようにもなります。
生き抜く力が身につく
近年、社会は激しく変化しています。その変化に対応するためには、コミュニケーション能力や自身で物事を判断して行動する能力など非認知能力が重要です。非認知能力を鍛えることで、社会を生き抜く力が身につくでしょう。
他者と協力したり友情を築いたりしやすくなる
非認知能力の要素には、コミュニケーション能力やリーダーシップなどの他者とつながる力があります。非認知能力を鍛えれば、将来子どもが関わる他者との友情や協力関係を構築しやすくなるでしょう。
犯罪率が下がる
自制心やメタ認知などの非認知能力が鍛えられると、感情任せにならず、自分の考えを冷静に捉えることができるため、犯罪を犯そうという思考が抑制されます。結果、子どもの非認知能力が高ければ、犯罪率が下がります。
非認知能力は幼児期に鍛えることが重要
なぜ幼児期に非認知能力を鍛えるのかというと、幼児期は脳の発達が著しいため、非認知能力も発達しやすいからです。
また、非認知能力は認知能力の学習面や、子どものさまざまな面の成長に関わるものであるため、より早い段階から鍛えておくと、その後の成長によい影響が得られます。非認知能力を鍛えるために幼児期は重要な時期と考えられます。
子どもの非認知能力を鍛える遊びや行動の具体例
子どもの非認知能力を高めることには、多くのメリットがあります。非認知能力は、日々の遊びや行動でも育まれるため、次の内容を参考に実践してみてください。
水遊び
水遊びは体を動かせる遊びです。遊びを通じて子どもの五感や好奇心も刺激されるため、非認知能力が鍛えられます。また、自然と関わる遊びは、思ったとおりにできないこともあり、うまく遊ぶための想像力や応用力を養うのにも効果的です。
ごっこ遊び
ごっこ遊びで役になりきるためには、日々さまざまなものを観察してまねることが必要です。遊びながら、想像力や共感性が鍛えられるでしょう。また、保護者や友達と遊ぶ場合は、コミュニケーション能力や協調性も養われます。
おもちゃ遊び
おもちゃ遊びは、認知機能や創造力、集中力、観察力、工夫する力など多くの非認知能力を鍛えられます。おもちゃのなかでも、これらの能力を鍛えるのにより適したものは、ブロックや積み木、粘土などです。この他にも非認知能力の育成に特化した知育玩具もあります。
工作
工作は、いろいろな材料を使って自由に遊ぶことで、想像力や創造力が鍛えられます。自宅にある材料を使って遊べるので、取り入れやすい遊びの1つです。子どもが集中しているときにはなるべく声をかけず、けがなどの危険がないかぎり口や手を出さないようにして、好きなように遊ばせるようにしましょう。
お絵かき
お絵かきは、一から自分の好きなものを描くことで、表現力や工夫する力、想像力や集中力などが鍛えられます。また、自身の感情を表現したり管理したりする能力や、創造力も身につくでしょう。
絵本の読み聞かせ
絵本でさまざまな物語に触れると、想像力や共感性、倫理観や集中力などが鍛えられます。寝る前に読み聞かせをするなど、習慣化するのもおすすめです。また、親子で会話を交えながら読み聞かせをすると、子どもが思ったことを表現する力もつきます。
読書
読書は、自己肯定感や思考力、共感性や倫理観、向上心などが鍛えられます。ただし、自発的に読書をすることが重要です。親が選んだ本を強制的に読ませるのではなく、子どもが興味を持った好きな本を好きなだけ読めるようにしてあげましょう。
泥遊び
泥は水分量によって硬さが変わるため、遊び方にも幅があります。外で遊びたがる子どもに適した遊びで、泥に触れながら遊び方を工夫することで、思考力や創造力などが鍛えられるでしょう。
自然観察
身近な自然に触れ合うことも大切です。季節や天候によって自然が見せる表情は多様で、子どもの好奇心を刺激します。また、自然を観察するなかで生じた疑問を解消する過程で、思考力や問題解決能力が鍛えられます。
共通点探し
共通点探しとは、「りんご」と「いちご」は果物、「車」と「飛行機」は乗り物など、共通点を探す遊びです。この遊びでは、抽象的思考力が鍛えられます。まずは、共通点を探しやすいお題から始めて、徐々に難しいお題に取り組みましょう。
ボール遊び
ボールは、工夫次第でさまざまな遊び方ができます。そのため、遊び方を考える過程で、想像力が鍛えられるでしょう。また、保護者や友だちと遊ぶ場合は、コミュニケーション能力や協調性、自制心も身につきます。体を動かし、体力もつくのでおすすめです。
料理
料理は、作業全体を通して計画性や効率性、想像力や思考力、問題解決能力などが鍛えられます。他者と料理する場合は、コミュニケーション能力や協調性も身につくでしょう。さらに、家族などの誰かに自分がつくった料理を食べてもらい喜んでもらえると、自己肯定感も高まります。
ボードゲーム
オセロや将棋などのボードゲームは、思考力や集中力、問題解決能力などが鍛えられます。遊び方を工夫できるボードゲームもあるため、まずは簡単な遊び方から始めましょう。
音楽遊び
音楽遊びは、音楽を聴いて楽しみながら、リズム感や想像力が養われます。特に、リズミカルな曲やクラシックは、非認知能力を鍛えるのに適しているとされています。また、自分の動作で音を出せる楽器やおもちゃを一緒に使うのもおすすめです。
子どもの非認知能力を鍛える際のポイント
子どもの非認知能力を鍛えるには、次のポイントに配慮するようにしましょう。
子どもの興味関心を考慮する
遊びは、大人が選んでやらせるのではなく、子どもが興味を持ってやりたいと思えることが重要です。興味があれば意欲的に遊ぶようになり、楽しみながら想像力や探究心、自主性などの非認知能力を向上させられます。
安心して安全に遊べるようにする
子どもが夢中になって遊べるように、安心できる環境を整えましょう。過度に関わるのではなく、愛情を持って見守ることで、子どもは自由に安心して遊べるようになります。ただし、子どもがけがをしたり事故を起こしたりしないように、安全に遊べる環境を用意するようにしましょう。
積極的に褒める
非認知能力を鍛えるためには、自己肯定感が重要で、保護者の接し方が子どもの自己肯定感に大きく影響します。自己肯定感を高めるには、注意する際も否定的な言い方や強制するようなことは言わずに、子どもの行動を褒めたり、自主的な行動を導いたりするような声かけをしましょう。
他者と交流する場を設ける
非認知能力のなかには、他者と関わることで成長する分野があります。他者と交流するなかで、生きていくために重要な非認知能力を鍛えられるでしょう。より効果的に子どもの非認知能力を鍛えたい場合は、家族以外の他者と交流する場を積極的に設けるのがよいでしょう。
子どもに主導権を渡して選択してもらう
保護者が子どもにやってほしい非認知能力を鍛えられる遊びが、子どもにとって効果的であるとは限りません。子どもが自身で選択して遊んだ内容こそが、非認知能力の向上に効果的です。
また、遊びに限らず日常生活でも、子どもに選択させることは、自身で考える機会になります。また、自分で選んだことを受け入れてもらうことで自己肯定感につながるでしょう。
保護者がお手本になる
子どもは、保護者の言動をまねします。そのため、保護者は子どものお手本となるように行動することが重要です。子どもの非認知能力を鍛えるためには、保護者の非認知能力を鍛えることも必要です。
感情的な行動を抑えられるよう訓練する
子どもは、遊んでいる途中で感情的な行動を取ることがあります。このような場面で自身を律する能力も重要な非認知能力です。保護者は子どもが感情的に行動しないように、自身の感情を認識して自己規制できる方法を教え、訓練するサポートをしましょう。
子どもの非認知能力を鍛える際の注意点
子どもの非認知能力を鍛える際には、次のようなことに注意しましょう。
遊びを強制しない
遊びを通して子どもの非認知能力を鍛えるためには、あくまで子どもが自主的に行動することが重要です。保護者が遊びを強制すると、非認知能力が向上しないだけでなく、その遊びを嫌いになる場合もあります。
子どもにさせたい遊びがある場合でも強制するのではなく、誘ったり、促したりして興味を向かせるようにしましょう。
完璧を求めない
非認知能力を鍛えることを意識しすぎて、子どもに完璧を求めないようにしましょう。非認知能力とは、完璧を求めることとは反対に、失敗したり壁にぶつかったりしても、諦めずに最後までやり遂げる能力です。そのためには、失敗していい、失敗は怖くないという環境を用意することが保護者に求められます。
完璧を求めて子どもが失敗を恐れるようになると、子どもの非認知能力が失われてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
まとめ
非認知能力とは、人の内面的な能力で、人格形成に関わるものとされています。諦めずに最後までやり遂げる能力でもあり、勉強やビジネスの場面にも影響するとされています。また、知識や技能、思考力を指す認知能力とも相互関係にあるため、非認知能力を高めることは学力の向上にもつながります。
非認知能力は日々の遊びで育むことができます。ただし、遊びは強制せず、子どもの興味を引き出して、楽しみながら鍛えられるようサポートしましょう。
お子さまが、非認知能力を鍛える遊びのなかで英語に興味を持った際は、「Sanrio English Master」を活用した英語教育もぜひご検討ください。
Sanrio English Masterは、専門家の知見とサンリオの創造性を活かし、どの年齢のお子さまでも楽しく学べる教材・知育玩具を実現しました。レッスンは、成長段階に合わせた内容で、英語表現を遊びながら学べます。自然に英語のアウトプットができるようにもなっており、インプットとアウトプットの繰り返しでコミュニケーション能力が培われます。
まずはお気軽に無料サンプルや無料教材体験で、Sanrio English Masterをお試しください。