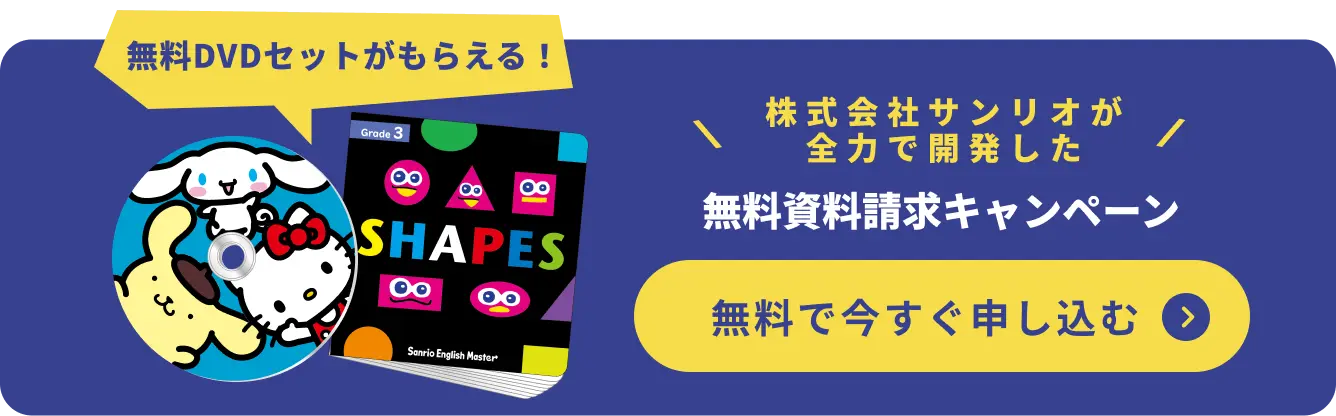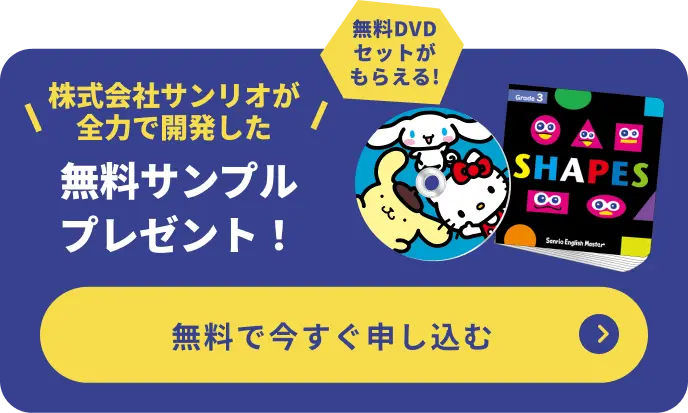3歳頃のイヤイヤ期への対処法は?イヤイヤ期におけるおうちの方の心構えも解説!

イヤイヤ期には個人差がありますが、一般的には1歳後半から始まり、3歳頃まで続くといわれています。3歳のお子さまは行動範囲も広がっているため、イヤイヤ期の対処に苦労しているおうちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、3歳頃のイヤイヤ期の特徴や適切な対処法を解説します。イヤイヤ期におけるおうちの方の心構えについても触れているので、ぜひ参考にしてください。
目次
イヤイヤ期とは?
イヤイヤ期とは、自己主張が強くなり「イヤ」「自分でやる」という言葉が増えてくる時期のことです。お子さまは3歳頃になると、思考力も急速に発達するため「自分で何かをしたい」と考えるようになります。また、イヤイヤ期には身体的な発達も重なって、行動できる範囲も広がります。
おうちの方にとっては苦労の多い時期ですが、主観と客観の分化や母子分離の始まりであり、お子さまの自我や精神の発達に欠かせない重要なプロセスだといえるでしょう。
3歳頃のイヤイヤ期が厄介な理由
「魔の2歳児」という言葉は広く知られていますが、3歳になってからもイヤイヤ期がおさまらず、さらに激しくなるといったケースも少なくありません。まずは、3歳頃のイヤイヤ期が起こる理由から見ていきましょう。
自我が芽生えるため
3歳頃は自我が芽生え始める時期であり「第一次反抗期」とも呼ばれます。他者との違いに気づき、自身を独立した存在として認識できるようになることで、自己主張が増えてくる点が特徴です。気持ちを言語化する能力も発達するため、自分の要求を伝えられるようになり、強い意志を持って要求を押し通そうとすることもあります。
物事に取り組むやる気が発生するため
自我の芽生えにより、3歳頃のお子さまは好奇心も育まれます。また、語彙の増加や身体の成長に伴い「自分で何かをしたい」という欲求が強くなる時期です。さまざまな物事に積極的に取り組む一方で、欲求が叶わない場合には、反抗的な態度をとってしまうこともあります。
感情や行動のコントロールが未発達なため
3歳頃のイヤイヤ期は、身体の成長に対して感情や行動のコントロールが未発達なことも特徴です。3歳頃になると、大人の言葉を理解したり、目的を持って行動したりすることが増えていきます。しかし、理性や我慢を司る脳の部位である前頭前野が未発達の状態にあるため、感情や行動のコントロールが上手くできず、癇癪を起こしやすくなります。
3歳頃のイヤイヤ期の特徴
続いては、3歳頃のイヤイヤ期の特徴を解説します。3歳児は語彙力も高まるため「イヤ」という言葉を使うだけではなく、さまざまな言動で自分の気持ちを表現するようになります。
自己主張が強い
3歳児は、自我の芽生えに加えて言語能力も発達するため、自己主張が強くなりがちです。2歳まではおうちの方の意見を聞き入れてきたお子さまでも、自分の欲求や意見を通そうと頑固になる場面が増えてくるかもしれません。
大人の真似をしたがる
3歳になる頃には、運動能力が発達し、手先も器用になってきます。「箸を使って食事をする」「靴を自分で履く」など、大人の真似をしたがって、さまざまなことに挑戦する場面も増えるでしょう。しかし、大人と同じようにできないことも多いため、そのギャップでストレスが溜まり、感情が爆発してしまうことがあります。
大人の言うことを聞かない
3歳頃のイヤイヤ期の特徴のひとつに「大人の言うことを聞かない」といった点が挙げられます。語彙力が高まることで、言葉による意思表示の幅が広がり、大人の意見や指示に対して反抗するケースは少なくありません。
例えば「今日は公園に行くから動きやすい服装にしようね」と伝えた場合、単純に「イヤ」というだけでなく「わたしはこっちの服がいい」と明確に拒否をすることが増えていきます。
反論や言い訳が多くなる
反論や言い訳が多くなるところも、3歳児ならではの特徴です。語彙が増えて大人との会話が可能になることで「でも」「だって」といった否定的な言葉を使う頻度が高まります。しかし、表現力や話し方は未熟であるため、欲望を適切に伝えられないケースも少なくありません。
自分の気持ちを上手に伝えられなかったり、思い通りの状況にならなかったりすると、イライラして癇癪を起こしてしまうこともあります。
自己中心的になる
イヤイヤ期のお子さまの言動は、おうちの方から見ると「自己中心的」に感じるかもしれません。しかし、3歳児は他者の感情や視点を含めて物事を考えることが難しく、どうしても自身の欲求を優先しやすくなります。自分の利益を第一に考えることは、標準的な成長・発達のプロセスであるため、3歳の時点で自己中心的な性格であっても、過度に心配する必要はありません。
暴力的になる
言葉にすることが苦手なお子さまや、不満を溜め込んでしまうタイプのお子さまは、暴力的な行動をとってしまうこともあります。手で叩いたり足で蹴ったりするほか、物を投げたり壊したりすることで、イライラした気持ちを発散します。
感情の起伏が激しくなる
イヤイヤ期のお子さまは、感情の起伏が激しくなりやすいといわれています。そのため、急に泣き出したり怒りだしたりすることが珍しくありません。「今日はテレビに好きなキャラクターが出てこなかった」など、おうちの方からすると小さなことに思えても、お子さまは気持ちの切り替えができず癇癪を起こしてしまうことがあります。
3歳頃のイヤイヤ期に対する適切な対処法
では、3歳児の反抗や癇癪にどのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、3歳頃のイヤイヤ期に対する適切な対処法を解説します。
お子さまの発言をよく聞く
イヤイヤ期のお子さまと接するときは、発言を頭ごなしに否定せず、耳を傾けて聞いてあげることが大切です。「静かにしなさい」「それはだめ」と言いたくなるかもしれませんが、お子さまの気持ちが落ち着くまで待つことを心がけましょう。お子さまが「自分の気持ちを分かってもらえている」と感じられるようになると、よりよい解決策を見つけやすくなります。
選択肢を与えて選ばせる
お子さまに選択肢を与えて、最後の意思決定を委ねることも効果的です。例えば「早く服を着なさい」というのではなく、2種類の洋服から好きな方を選ばせるといった方法が挙げられます。「自分で何かしらを決めた」と感じることができれば、お子さま自身も満足感が得られます。
安全を確保したうえで自由にさせる
安全を確保しやすい家庭内なら、お子さまをある程度自由に行動させるのもおすすめです。お子さまが自分で何かを成し遂げられれば、成功体験として自立につながります。また、失敗を経験することも心身の成長には欠かせません。しかし、家庭内と公共の場との違いが完全には理解できない年齢でもあるため、危険な行為を見かけたときは、必ず声をかけるようにしましょう。
言い聞かせ方を変える
「繰り返し伝えているのに、まったく本人に届かない」といった悩みを抱えている場合は、言い聞かせ方を変えると改善が見込めるかもしれません。例えば「しなさい」といった命令口調で話すのではなく「してね」など、お子さまに寄り添った口調で言い聞かせることで、お子さまの言動にポジティブな変化が生まれる可能性があります。
お子さまが納得するまで付き合う
納得するまで付き合うことは、イヤイヤ期に対する適切な対処法のひとつです。例えば、靴を上手く履けなくて苦戦している場合、おうちの方が手伝ってしまうと「自分でできるのに!」と癇癪を起こしてしまう可能性があります。時間に余裕があるときは、お子さまの様子を見守り、達成感が味わえるようにしてみましょう。
お手伝いをしてもらう
何かを頼まれて完遂できれば、お子さまは充実感や満足感が得られます。お子さまでも完遂できるようなお手伝いをしてもらうことは、自己肯定感を高めることにもつながります。「食事の前に箸を並べる」「玄関の靴をそろえる」など、簡単なことから始め、少しずつできることを増やしていきましょう。
ルーティーンを作ってあげる
3歳頃になると、決まった流れで物事を進めると精神的に安心感を得やすいといわれています。そのため、イヤイヤ期の軽減にルーティーンを取り入れることも考えてみましょう。
例えば「30分テレビを見たら夕食」「夕食後はすぐお風呂」など、シンプルで分かりやすい習慣を作ると、お子さまが見通しを持ちやすくなり、スムーズに行動できるようになります。結果的に、おうちの方の負担も減るかもしれません。
3歳頃のイヤイヤ期に対する不適切な対処法
ここでは、3歳頃のイヤイヤ期に対する不適切な対処法を解説します。お子さまとの接し方を少し見直すだけで、よい変化がもたらされるかもしれません。
できないと決めつけてしまう
おうちの方ができないと決めつけて行動を制限してしまうと、反抗心が強くなるだけでなく、お子さまの興味や意欲の減退を招きます。できなかったことにもう一度挑戦する過程や、成功体験を積み重ねることは、お子さまの成長にもつながります。失敗を恐れず、前向きに取り組む土台をつくるためにも、干渉しすぎないことを心がけてみましょう。
感情的に対応してしまう
イヤイヤ期はおうちの方のストレスも溜まりやすくなるため、お子さまと接しているなかで感情的になってしまうこともあるでしょう。また「道路に飛び出す」「ほかの子どもを傷つける」などのケースでは、強い口調での注意が必要となるかもしれません。しかし、強制的に行動させたり、怒鳴って叱責したりすると、状況がさらに悪化する可能性があるため、まずはおうちの方が深呼吸をして落ち着くことを意識してみてください。
イヤイヤ期におけるおうちの方の心構え
イヤイヤ期は、ずっと続くものではありません。個人差はあるものの、4歳から落ち着いてくるお子さまも増えるため、期間限定のものだと考えて乗り切っていきましょう。ここでは、イヤイヤ期におけるおうちの方の心構えについて紹介します。
感情的にならず冷静に対処する
お子さまが反抗的な態度をとるのには理由があるため、感情的にならずに冷静に対処しましょう。冷静になるのが難しい場合には、その場から離れてお子さまと物理的な距離を置くのも効果的です。「隣の部屋に移動する」「トイレに行く」など、少しでも一人になれる時間があると、心を落ち着かせやすくなります。
スケジュールに余裕を持たせる
お子さまの要望を叶え、行動を制限しないためには、スケジュールに余裕を持たせることが大切です。例えば、家を出発する30分前から準備をすることで、服のボタンを留めたり、靴を履いたりする姿を見守ってあげやすくなります。スケジュールに余裕があると、おうちの方の精神的な負担も軽くなるでしょう。
時には、お子さまの気持ちを尊重してあげる
イヤイヤ期のお子さまの行動をすべて予測することはできないため、適切な対処法を試しても、どうにもならない場合があります。おうちの方は「どうしようもないときもある」と知っておくことで、気持ちにゆとりが生まれます。3歳児の小さな身体で一生懸命何かを訴えようとしていることを理解し、お子さまの気持ちを尊重してあげましょう。
イヤイヤ期だからこそ楽しく達成感を味わえる教材を!
イヤイヤ期は、お子さまの自我が芽生え、自分の意志を強く持ち始める時期です。視覚・聴覚・触覚などの感覚も急速に発達するため、目を引く色や動き、楽しい音に強い反応を示すようになります。イヤイヤ期だからこそ、楽しく達成感を味わえる教材を取り入れることで、お子さま自身の気持ちにも前向きな変化がもたらされるでしょう。
Sanrio English Masterのメインキャラクター「エディ」は、実証実験の結果をもとに、お子さまの興味・関心を引き出すようにデザインされています。お馴染みのサンリオキャラクターズも登場するので、楽しみながら英語を学ぶことが可能です。動画のアニメパートでは、エディ自身が「イヤイヤ」と自分の気持ちを伝えるシーンもあるものの、家族と一緒に乗り越えていきます。
また、絵本で描かれている「エディが野菜を食べたくない」と駄々をこねる話では、植物を育てるという解決策を見つけます。このように、Sanrio English Masterは、お子さまの成長と一緒にエディも成長するように描かれており、生活習慣や社会のモラル、ルールについて学べる点もポイントです。
学習と遊びを両立させることで、お子さま自身の考える力も育つため、親子の信頼関係を深める効果も期待できます。アウトプットの機会も豊富にあるので「お子さまの言葉の発達をサポートしたい」という方にもおすすめです。無料サンプルもあるので、ぜひ気軽にお試しください。
まとめ
イヤイヤ期は、お子さまの成長の証であり、チャレンジ精神や主体性を育むチャンスでもあります。反抗的な態度をとることも増えるため、おうちの方にとっては苦労の多い時期ですが、お子さまの気持ちに寄り添いながら乗り切っていきましょう。
Sanrio English Masterでは、イヤイヤ期のお子さまと一緒に楽しめるさまざまな教材をご用意しております。知的好奇心を刺激する内容となっており、お子さまの「もっと知りたい!」という気持ちを引き出す工夫が施されているので、遊びながら英語にも知育にも取り組めます。無料の教材体験キャンペーンも実施しています。まずはお気軽にお問い合わせください。