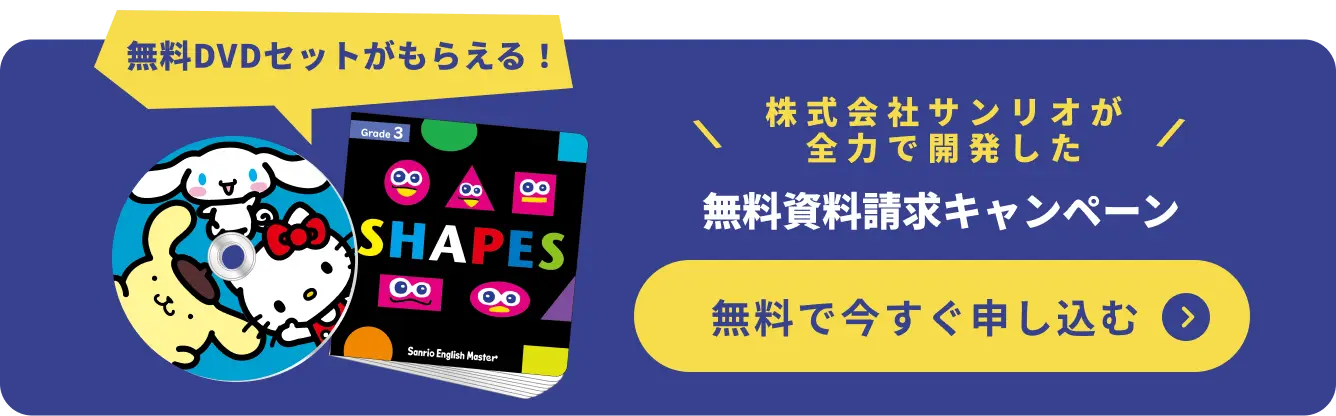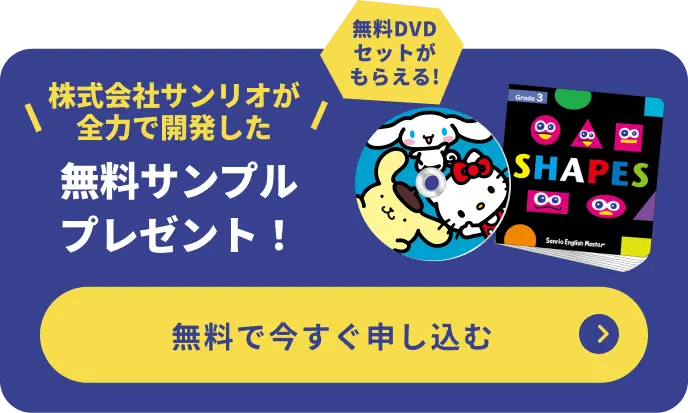指差しはいつから?種類や指差しをしない原因・障害との関係も解説

赤ちゃんの成長の過程において、指差しはコミュニケーションの力を育むために必要な動作です。ただし、成長には個人差があり、指差しの時期が遅れる可能性があります。
この記事では、指差しの始まる時期や種類、指差ししない原因などを解説します。指差しを促すおすすめの方法も解説しているため、ぜひ参考にしてください。
目次
指差しとは
指差しとは、赤ちゃんの非言語コミュニケーションの1つです。言語を使わずに興味や要求を示すために、対象のものや方向を指します。指差しには伝えたい気持ちが表れており、言葉の能力の向上につながるため重要です。指差しは赤ちゃんの成長に応じて変化し、さまざまな意味をもつようになります。
指差しはいつから始まる?
一般的に、指差しは10か月から11か月頃に始まります。興味のある対象を指で差し、コミュニケーションとしての意味をもつとされています。赤ちゃんの指差しに反応すると、社会性や言語の能力の向上につながるでしょう。ただし、生後9〜15週頃の指を立てる動作には、コミュニケーションの意図がありません。指差しと混同しないように注意が必要です。
【時期】指差しの種類
指差しは、時期ごとに意味が異なります。ここでは、指差しの種類を解説します。
【10~11か月】興味
興味の指差しは、興味の対象に指を向ける行為です。たとえば、犬や花などを見つけたとき、対象に指を向けます。また、相手の興味を察して、視線の先と同じ方向を見る場合もあります。赤ちゃんに推測の力が身につき、相手の興味を理解できるようになった証拠です。ただし、周囲に人がいなくても、指差しをする場合があります。
【10~14か月】要求
要求の指差しは、自分のほしいものを相手に伝える行為です。たとえば、周囲の人におもちゃや食べ物などを指差し、自分の意思を伝えます。指を向けるだけでなく、一緒に声も出して要求する行動もみられます。指差しをした際は、周囲の大人たちが言葉と一緒に反応してあげることが大事です。
【12~18か月】叙述
叙述の指差しは、興味や感情を分かち合いを求める行為です。周囲に見つけたものを知らせて、自分と同じものを一緒に見てほしいと要求します。別名で共感や感動、定位の指差しともいわれています。叙述の指差しが始まると、赤ちゃんの社会性が発達していると考えてよいでしょう。
【18か月~】応答
応答の指差しは、質問や意思に対して答えを示す行為です。赤ちゃんに質問をして、双方向のコミュニケーションが成り立つ状態を指します。たとえば、絵本を見ながら質問した場合に、対象のものを指で示せるでしょう。応答の指差しができると、赤ちゃんの指差し行動が完成したと考えられます。
指差しをしない原因
赤ちゃんによっては、指差しをしない場合があります。ここでは、原因を解説します。
手差しをしている
手差しとは、指の代わりに手全体を使って指すことです。手を動かすコミュニケーションは、指差しができる手前の段階なため問題ありません。赤ちゃんの成長の度合いによっては、指先が器用に動かせないケースが多々あります。手や指の動かし方には個性があるため、手差しを肯定的に受け入れることが大事です。
発達には個人差がある
赤ちゃんの発達には個人差があるため、特定の期間に指差しが始まらない場合があります。身体的な成長が遅いために、指差しが遅れているケースも考えられます。1歳半健診では、指差しで言葉や社会性の発達の度合いを判断しましょう。指差しが遅れていることに不安な場合は、周囲の人がサポートすることが大事です。
聴覚機能に問題がある
赤ちゃんが指差しをしない場合、耳の聞こえに問題がある可能性が考えられます。相手からの呼びかけに応えられず、指差しができない場合もあるためです。耳が悪い場合、言語の習得をはじめとする発達が遅れるケースがあります。聴覚機能に問題がある場合、絵やイラストを使った、視覚的なコミュニケーションでサポートすることをおすすめします。
指差しと障害の関係
赤ちゃんが指差しをしない場合、発達障害をもつ可能性も考えられます。発達障害とは、子どもの発達の過程で問題が起こることです。共同注意という、他の人と同じものを見る力が育ちにくくなり、指差しをしない場合があります。子どもの発達によっては、理解や行動する過程で問題が起こり、生活や学習上の問題につながるでしょう。
たとえば、言葉の意味がわからなかったり、人の真似ができなかったりするなどのケースがあります。発達障害は、知能の発達にも影響するため、家庭での育て方に注意が必要です。
指差しとASD(自閉スペクトラム症)の関係
指差しの発達は、ASD(自閉スペクトラム症)やクレーン現象と関係しています。ここでは、その関連性について解説します。
ASD(自閉スペクトラム症)とは
ASDは、コミュニケーションや対人関係などに問題を抱える発達障害の1つです。ASDの症状をもつ子どもは人に対する関心が低く、指差しをしない場合があります。ただし、ASDの症状には個人差があるものです。年齢や環境によって変化する場合があるため、自己判断での断定は避けましょう。
クレーン現象
クレーン現象とは、人の手を使って物を指したり、取らせたりしようとする行為です。この現象は、指差しをはじめとした、意思伝達が苦手な子どもに多い傾向にあります。クレーン現象が起きやすいのは、他の人を気にせずに自分が達成したい物事のために動く傾向があるためです。ただし、1〜3歳の子どものクレーン現象は、必ずしも発達障害ではありません。
指差しを促すおすすめの方法
指差しは、お手本を見せたり、一緒に遊んだりすると促せます。ここでは、おすすめの方法を解説します。
先に親が指差しをする
親が指差しをすることで、赤ちゃんが真似しやすくなります。赤ちゃんにとって真似するのは楽しく、自分でも指差しをしたくなるためです。先にお手本を見せると、指差しでのコミュニケーションに慣れやすくなるでしょう。赤ちゃんに指の形を作らせて、話しかけながら一緒に指差しをするのもおすすめです。
子どもの指差しに反応する
赤ちゃんの指差しには、周囲の人が反応を見せることが大事です。たとえば、犬に指差ししたら「わんわんがいるね」、花に対して「きれいだね」などと応えてあげるとよいでしょう。反応を見るとうれしくなり、もっと周囲の人と気持ちを共有したくなります。コミュニケーションのきっかけにもなり、要求や意思を伝える方法として指差しを始めやすくなります。
遊びながら指差しを促す
指差しは遊びのなかで自然に覚えられます。赤ちゃんの好きなもので繰り返し指差しをすると、要求のために真似しやすくなります。少し距離のある見えるところに興味のあるものを置き、赤ちゃんが指差しをしてから取ってあげるのも大事です。絵本やおもちゃなどで、2つ見せて、好きな方を選ばせると指差しをより覚えやすくなるでしょう。
テレビや動画の視聴を控える
テレビや動画は一方通行で情報を伝えるため、コミュニケーションが生まれにくいものです。コミュニケーションの力は、反応を見ながら言葉を使うことで向上します。言語能力や社会性を育むためには、テレビや動画の視聴を控えることが大事です。コミュニケーションの楽しさを覚えると、指差しをしやすくなります。
まとめ
指差しは、生後10か月から11か月頃に始まります。指差しの意味は時期によって異なるため、反応したりコミュニケーションを取ったりしましょう。ただし、子どもの発達の度合いによって、指差しをしないケースがあります。お手本を見せたり、絵本やおもちゃなどを使ったりして、指差しを促しましょう。
サンリオは、お子さまとおうちの方が遊びながら、英語にも知育にも取り組める教材を扱っています。エンターテインメント性のある教材を使って、自然とお子さまの興味・関心を引き出せます。英語教材を購入する際は、ぜひ利用をご検討ください。