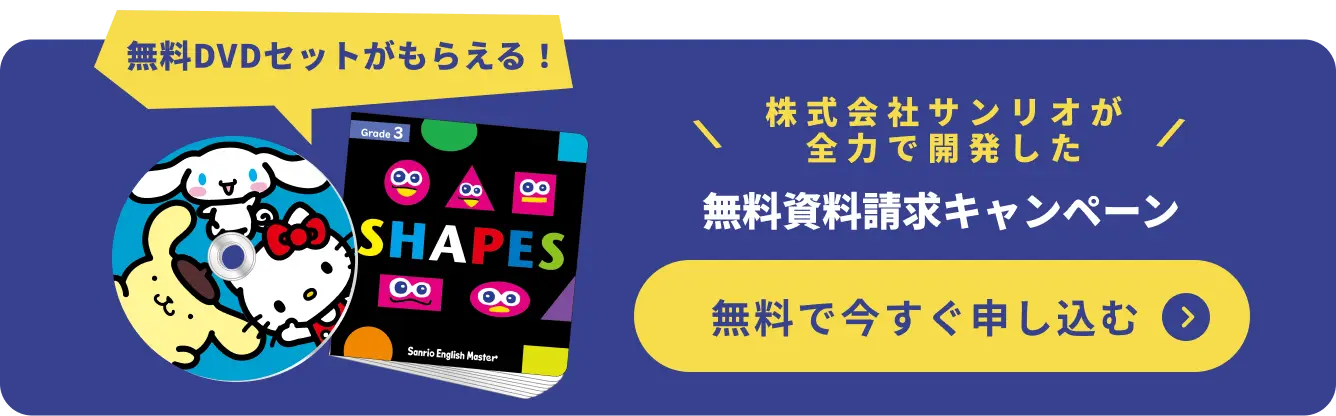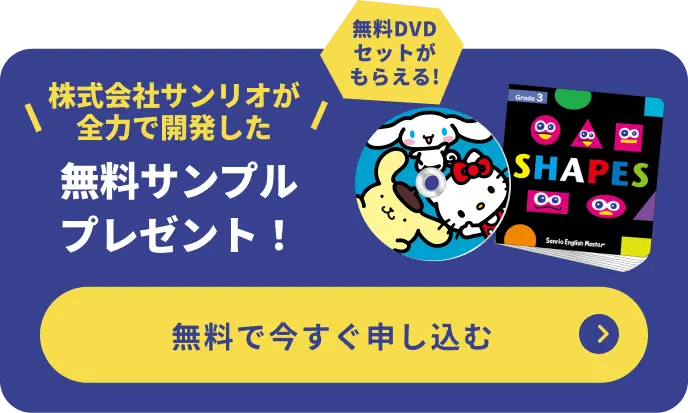赤ちゃんは何歳からしゃべる?年齢別の目安や意識すべきポイントについて解説

赤ちゃんが何歳から話し始めるかについて、気になっている方がいるかもしれません。結論から伝えると、お子さまによって、しゃべり始めるタイミングは異なります。
当記事では、赤ちゃんがしゃべり始める時期の目安やおうちの方が意識すべきことなどについて解説します。赤ちゃんの発語に関心があるおうちの方は参考にしてください。
目次
赤ちゃんは何歳からしゃべる?目安は生後9か月~1歳半
赤ちゃんが話し始める時期に、明確な基準はありません。それは、発達には個人差があるためです。
ただし、目安はあります。平成22年に発表された厚生労働省「乳幼児身体発育調査」のデータによれば、一語以上の言葉を話す乳幼児の割合は生後9~10か月未満で9%、生後1年0~1か月未満で57.6%、生後1年6~7か月未満で94.7%です。
そのため、おおよそ生後9か月~1歳半がしゃべり始める目安と考えられます。
赤ちゃんの言語に関する発達目安
ここでは、赤ちゃんの言語に関する発達目安について解説します。
生後0~1か月
生後0~1か月の赤ちゃんは、主に泣くことで周囲とコミュニケーションを取ります。この時期の泣き声は、空腹や排泄による不快感など、生理的な要求を訴えるための手段です。生まれたばかりではありますが、周りの音や声を感じ取りつつ泣いて要求を伝えています。
生後2~3か月
生後2~3か月になると、赤ちゃんは「クーイング」と呼ばれる行動を始めます。クーイングとは、赤ちゃんによる口腔(口からのどまでの空洞部分)を使った音声表現で「うー」や「あー」といった母音を発することです。
クーイングは、赤ちゃんが安心してリラックスしているときや、ご機嫌なときにみられます。
生後4か月
生後4か月頃になると、赤ちゃんは母音だけでなく子音も使い始めます。「ぶー」や「ばー」といった音が聞かれるようになり、声を出す行為がさらに多様化する点が特徴です。
また、この頃の赤ちゃんは、手足の動きと合わせて笑ったり声を出したりすることが増えます。
生後5~6か月
生後5~6か月になると、赤ちゃんは喃語(なんご)を話し始めます。喃語とは、子音と母音を組み合わせた「だだだ」「ばばば」といった音のことです。成長に応じて徐々に、発する喃語の種類も増えていきます。
喃語そのものには特定の意味がないものの、赤ちゃんが声を使って周囲と関わろうとする大事な段階です。
1歳前後
1歳前後になると、赤ちゃんは「まんま」や「わんわん」など一語文を話し始めます。
この時期になると、発した言葉とその意味を結び付ける能力が発達してくる点をおうちの方は押さえておきましょう。例えば「まんま」といえば「食べ物を指す」といった形です。これにより、赤ちゃんは言葉を使って自分の気持ちや欲求を伝え始めます。
生後1歳半〜2歳半
生後1歳半〜2歳半になると、赤ちゃんは単語を組み合わせて「ママ、きた」「わんわん、いる」などの二語文を話せるようになります。この段階では、問いかけに対して答える力も備わり、意思疎通がさらにスムーズになるでしょう。
また、自分の意思をより具体的に伝えられるようになります。ときには「いや」といった否定的な表現を使うことも増えます。
赤ちゃんとの接し方で意識したいポイント
ここでは、赤ちゃんとの接し方で意識したいポイントについて解説します。
反応をしてあげる
赤ちゃんの「話したい」という思いを育んでいくためには、赤ちゃんの言葉や声にしっかりと反応してあげることが重要です。
例えば、クーイングをする生後2か月から、一語文を話す生後1歳前後までは、赤ちゃんが発した言葉をそのまま真似してあげるとよいでしょう。これによって、赤ちゃんは「自分の声が相手に届いている」と感じ、楽しんで声を出してくれるでしょう。
積極的に話しかける
赤ちゃんと接する際には、おうちの方から積極的に話しかけてあげましょう。
赤ちゃんが興味を示したモノに対して、名前を教えたり、簡単な説明をしてあげたりすることで、単語と意味を結び付ける力が育まれます。この取り組みを繰り返すことで、赤ちゃんの語彙はどんどん広がっていきます。
また、赤ちゃんの行動を「今、○○しているね」と実況中継することも効果的です。赤ちゃんに近づいて、ゆっくりとはっきり話してあげましょう。
ポジティブな言葉を心がける
赤ちゃんとのコミュニケーションでは、ポジティブな言葉を意識することが大切です。否定的な言葉を用いると、赤ちゃんが消極的な性格に育つ恐れがあります。「~してはいけない」と禁止する言い方ではなく、「~しよう」と前向きな提案を心がけるとよいでしょう。
また、赤ちゃんが何かできたときには、しっかりとほめてあげることも忘れないようにしてください。
先回りをしない
赤ちゃんの行動や表情から何をしたいのか察することは親にとって自然な行動です。しかし、赤ちゃんが言葉を発する前に先回りして要求をかなえてしまうと、赤ちゃんが話すきっかけを失う恐れがあります。
赤ちゃんが自分の言葉で伝えようとする意欲を育てるためには、言葉での要求を待つ姿勢が大切です。「どうしたいの?」と優しく問いかけることで、赤ちゃんが言葉を使って気持ちを伝える練習になります。
間違いを正さない
お子さまが成長を通して覚えた言葉が間違っていたとしても、正したり何度も指摘をしたりするのは避けるべきです。繰り返し指摘されると、話すこと自体を嫌がるようになってしまう恐れがあります。
言い間違いをしていたとしても、成長とともに自然と正しい言葉遣いへと変わっていくものです。正しい言葉を話させることよりも、多くの言葉を楽しく話せる環境をつくることが何よりも大切です。
赤ちゃんの言語発達をサポートするアイテム
ここでは、赤ちゃんの言語発達をサポートするアイテムについて解説します。
絵本
言語発達において、絵本の読み聞かせは視覚と聴覚の両面でよい影響を与えます。
赤ちゃんの頃から絵本を読んであげることで、自然と語彙が増え、言葉を覚える基盤が築かれます。擬音語や擬態語といったオノマトペが多く含まれる絵本を選ぶと、赤ちゃんの興味を引きやすく、言葉への関心が高まるため効果的です。
CD
赤ちゃんの言語発達をサポートするアイテムの1つは、CDです。
童謡や子ども向けの歌が収録されたCDを日常的にかけ流しすると、言語発達を促進する手助けとなります。BGMとして自然な形で赤ちゃんの生活に取り入れることで、言葉を徐々にインプットしていけます。
フラッシュカード
赤ちゃんの言語発達を促したいなら、フラッシュカードを用いましょう。フラッシュカードとは、表面にイラスト、裏面にイラストの名前が書かれたカードのことです。
フラッシュカードを順番にめくりながら、赤ちゃんにイラストの名前を伝えることで、目と耳の両方を使って言葉を学ぶことができます。赤ちゃんでも楽しみながら単語のインプットを進められ、遊び感覚で取り入れられる点が魅力です。
しゃべり始めるのが遅いときには
お子さまが言葉をしゃべり始める時期がほかの子どもより遅いと感じても、過度に心配しないようにしましょう。言葉を話し始める時期には個人差があり、早く話し始める子どももいれば、ゆっくり成長する子どももいます。遅れているように見えても、成長とともに自然に追いついていきます。
ただし、言葉の発達が極端に遅い、またはほかの発達面でも気になる点がある場合には、早めに専門家に相談することを検討しましょう。
発育に関する相談先
ここでは、発育に関する相談先を紹介します。
子育て支援センター
子育て支援センターは、お子さまに関するさまざまな悩みを相談できる施設です。発育や発達に関するアドバイスだけでなく、状況に応じて適切な専門機関やサービスの案内もしてくれるため、育児で悩むおうちの方の心強い味方となります。
また、同じ地域で子育てをするおうちの方同士や、お子さま同士の交流の場にもなります。
保健センター
保健センターは、お子さまの発達や発育に関することを相談できる施設です。
言語発達に関することだけではなく、保健指導や健康調査、健康教育など、健康面に関するさまざまなサポートも受けられます。育児に関する必要な支援を受けられる場所として、日常的に頼れる存在です。
まとめ
お子さまが何歳からしゃべり始めるかは、発達度合いや個性によって異なります。発達度合いがゆっくりであったとしても、焦ることなくお子さまと接し、しゃべるのを待ちましょう。お子さまが日本語に慣れてきたら、段階的に英語に触れていくのもおすすめです。
Sanrio English Masterなら、お子さまとおうちの方が共に遊びながら英語表現を覚えられます。自然に英語に触れられる環境を整えたいおうちの方は、まず無料サンプルをお試しください。