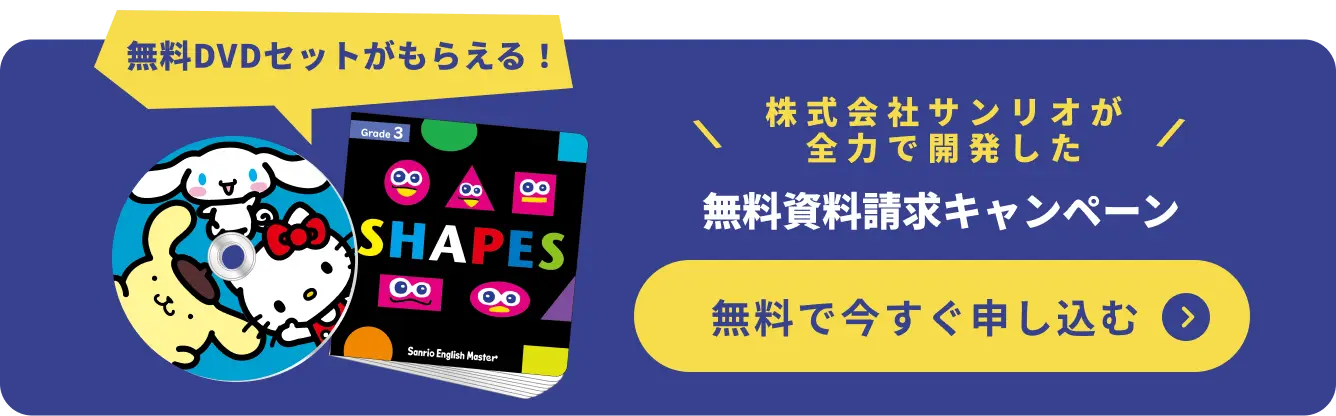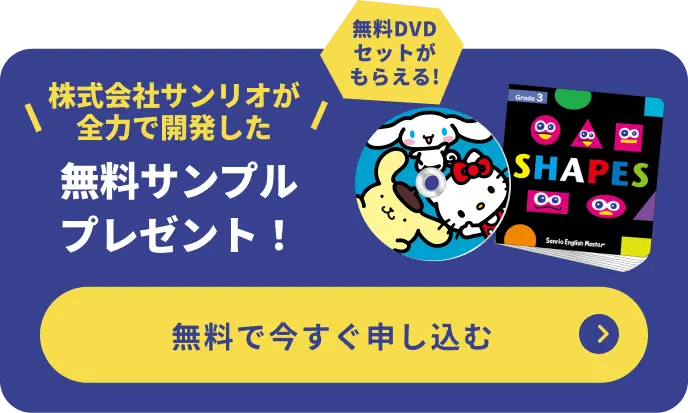非認知能力はこれからの時代に欠かせない力!概要と育て方、おうちの方の注意点を解説

近年「非認知能力」が注目されていますが、聞いたことはあっても、そもそも非認知能力とはどのようなものかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、非認知能力の概要と伸ばすための具体的な方法、おうちの方が注意したいポイントなどをわかりやすく解説します。非認知能力を知ることで、お子さまへの関わり方や子育てのヒントに役立ててください。
目次
非認知能力とはどのような力か
はじめに、非認知能力がどのような力なのか、似た用語との違いを踏まえながら解説します。
認知能力と非認知能力
非認知能力は、認知能力には当てはまらない能力を指す言葉です。
認知能力とは、数値化できる知的能力を指します。IQ(知能指数)やテストの得点・偏差値、計算力、記憶力、言語力などです。
一方の非認知能力は、数値で測れない「心の力」とも呼べる力で、認知能力以外の力を包括します。意欲や自信、協調性、共感性、自制心、さらにコミュニケーション能力や発想力などを含みます。
非認知能力のはじまり
非認知能力は、アメリカ・シカゴ大学の教授で経済学者であるジェームズ・J・ヘックマンの提唱以降、注目されるようになりました。
ジェームズ・J・ヘックマンは、ペリー就学前プログラムと呼ばれる実験結果を参考に、「就学前の幼児期に充実した教育を与えると、将来の経済的成功や安定が期待できる」との研究結果を発表しました。
ペリー就学前プログラムは、1960年代にアメリカで実施された実験です。2つに分けられた幼児グループの一方には教育を施しつつ他方は放任し、40年後までを追跡調査しました。その結果、教育を施されたグループのほうが、経済的に成功し、安定した生活を送っている割合が高いという結果になっています。
2015年、OECD(経済協力開発機構)が提唱した「社会情動的スキル」も、非認知能力と同様の力を指します。非認知能力は教育界だけでなく、世界の経済界も注目する大切な力といってよいでしょう。
非認知能力が注目を集めている社会的背景
非認知能力が注目を集めるきっかけとなった現代の社会的背景を、3つの観点から解説します。
長寿社会の到来
日本人の寿命が延び続け、長寿社会が到来しています。厚生労働省がまとめた日本人の平均寿命を示すグラフをみると、年々平均寿命は長くなっています。
そのため、長い社会生活を自分らしく豊かに歩むために、思考力やコミュニケーション能力、協調性、柔軟性など、非認知能力が果たす役割も大きくなっています。
参考:図表1-2-1 平均寿命の推移|令和2年版 厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-|厚生労働省
社会の激しい変容
変化の激しい現代社会では、予期せぬ事態にも柔軟に対応できる力として、非認知能力が重視されてきています。
また、文部科学省が新学習指導要領実施に際し提唱した「生きる力」の1つに「豊かな人間性」を挙げています。これも、非認知能力を養うことで身につく力であり、重要な能力であるといえます。
テクノロジーの発展
AIに代表されるテクノロジーは、すさまじい勢いで発展しています。こうしたテクノロジーの発展も、非認知能力が注目されるきっかけとなった背景の1つです。
現在、データの処理や記憶、単純作業は次々とAIに代替され、人の働き方も変化しています。そのため、これからの時代を生きるには、AIに代替されない力を持っていなければなりません。非認知能力はAIが参入できない、人間ならではのスキルです。
非認知能力で注目したい4つの力
非認知能力は、多様な力を包括する概念です。ここでは非認知能力のうち、特に注目したい4つの力をピックアップし、解説します。
自分を信じ、愛する力
自分を信じ、愛する力は「自己肯定感」「自己効力感」と呼ばれます。「〇〇だから、自分が好きだ」「△△だから、自分はすごい」と条件付きで信じ、愛するのではなく、ありのままの自分を肯定して受け入れ、愛する力です。
自分を信じる力があると、物事に積極的に挑戦し、失敗も糧にできるようになります。
自分と向き合い、コントロールする力
自分と正面から向き合って受け止め、適切にコントロールできる力も、非認知能力の1つです。自制心、理性とも呼ばれます。
自制心を持ち、理性のある行動が取れると、困難な状況でも冷静な対処が可能になります。生きる上で、厳しい状況に陥った場合でも、乗り越える力が身につくでしょう。
自分を高めようと努力できる力
自分を高めようと努力できる力は、意欲、忍耐力とも呼ばれます。夢中になる力とも言い換えられます。
この力があると、創意工夫や試行錯誤ができるため、成長のために自分を変化させることを恐れず、柔軟に生きていけるでしょう。
他者を尊重し、適切に関わる力
他者を尊重し適切に関わる力は、協調性や思いやりなどを指します。社会生活においては、この力が欠かせません。相手を理解し、相手の立場や考え方を尊重することで、円滑な人間関係が築けるようになるでしょう。
非認知能力を伸ばすために欠かせない要素
非認知能力を伸ばすとき、欠かせない要素が「アタッチメント」です。アタッチメントとは何か、また、スキンシップとの違いを解説します。
非認知能力に欠かせないアタッチメントとは
非認知能力を育てるためには、お子さまがアタッチメントに満たされていることが大切です。アタッチメントは「愛着」と訳される心理学用語で、特定の他者との心のつながりを指します。
幼少期に家族や信頼できる人にくっつき、心理的な安心感を十分に得られると、成長過程で非認知能力が育まれるとされます。
アタッチメントとスキンシップの違い
アタッチメントと概念が似た言葉に、「スキンシップ」があります。スキンシップは、肌を直接触れ合わせるコミュニケーションです。頬をくっつけたり、手をつないだりする行為が、スキンシップです。
一方アタッチメントは、相手に触れることで得られる安心感を指し、心の動きに注目しています。両者の違いを押さえ、非認知能力の養成にはアタッチメントが重要であると理解しましょう。
非認知能力を育てる最適な年齢
人間の非認知能力は、1歳頃から5~6歳頃の幼児期に、劇的に育つといわれます。幼児期は身体とともに、心も大きく育つ時期のため、この時期に、さまざまな心の動きとともに、非認知能力も育ちます。
ただし、非認知能力そのものは、何歳からでもトレーニングが可能です。自制心や協調性、忍耐力、人間関係スキルなどは、大人になってからのほうが鍛えやすい場合もあります。
そのため幼児期は、非認知能力の土台を育てる期間と考えるとよいでしょう。
非認知能力を育てる方法
ここからは、お子さまの非認知能力を育てる、具体的な方法を5つ解説します。
お子さまが興味を持ったこと・好きなことに取り組ませる
興味を持ったことや好きなことに対するワクワクする気持ちは、非認知能力の土台となります。お子さまの挑戦心や好奇心を刺激し育むために、興味を持ったことや好きなことは、応援してあげることが重要です。また、お子さま自身が「こうしてみよう」「これはどうかな?」と考え、工夫する力も養われます。
ただし、おうちの方が押しつけた場合には、やる気を失うきっかけになり得ます。あたたかく見守り、サポートする関わり方を大切にしてください。
日常生活でお子さまが活躍できる場面を用意する
非認知能力は、日常生活でも育てられます。お子さまが活躍できる場面、達成感を得られるシチュエーションを用意してみましょう。
おすすめは、お手伝いです。お手伝いは「ありがとう」「助かったよ」と感謝される経験を積めるため、自信がつきます。
また、友達と遊ぶときに相手のことを考えて「何をするか」と考える時間も、非認知能力の養成に有効です。
お子さまに決定権を持たせる
支障がない範囲で、お子さまに決定権を持たせる方法もおすすめです。決めることは、「何をして遊ぶか」「お昼ごはんは何を食べるか」など、身近なことで構いません。大切なのは、決定権が自分にあると、お子さまが感じられることです。決定権を持たせることは、「あなたの思いを大切にしているよ」というメッセージを伝え、お子さまの自己肯定感を高めます。
決定が間違っていても、失敗した過程から学びを得られます。お子さまが自分で決定したという事実を褒めることで、お子さまのモチベーションも維持できるでしょう。
ミスや失敗には前向きに声を掛ける
子どもは、初めての挑戦が多く、挑戦にはミスや失敗はつきものです。深刻に捉えず、ポジティブに変換できる声掛けでフォローしてあげましょう。
まずは「頑張ったね!」と挑戦を認める声掛けから入りましょう。挑戦した事実を認めることで、お子さまの落ち込む気持ちを浮上させます。「もう一度やってみない?」と再チャレンジを促したり、「次はこうしてみようか」と別のやり方を提案したりするのも、よい声掛けです。
努力の過程を認める
非認知能力を伸ばしたい場合、お子さまが見せた結果だけに注目しないよう注意しましょう。結果だけを褒めると、結果ばかりを追求し、過程をないがしろにするようになります。
お子さまの努力の過程も丁寧に見守り、まず「努力できていること」を十分に褒めてください。自分の頑張りを認めてもらい、褒めてもらうことで、お子さまのチャレンジ意欲や自己肯定感が高まります。
非認知能力を伸ばすために注意したい言動
非認知能力を伸ばすには、お子さまに最も近い存在である、おうちの方の言動が重要です。注意したいおうちの方の言動を、3つ解説します。
他の子どもと比べない
子どもの成長は、1人ひとりペースが異なります。この前提を理解し、同級生や兄弟姉妹など、他の子どもとお子さまを比べることは避けましょう。他の子どもと比べられ、もしできていなかったときは、お子さまが劣等感を抱いてしまいます。
お子さまができるようになったことを承認したい、成長を実感させたいなどの場合は、お子さまの過去と比べましょう。できるようになった点が見つかり、成長を具体的に伝えられます。
イライラを声や態度に出さない
子どもは、おうちの方の様子をよく見ています。そして、大人が思う以上に敏感で繊細です。
おうちの方のイライラした感情や態度は、お子さまに伝わり、萎縮させる要因となります。萎縮したままでは、心の力・非認知能力を伸び伸びと育てることは難しいでしょう。
まず、おうちの方が大らかにいられることを、大切にしてください。イライラをお子さまにぶつけそうになる前に、深呼吸して別のことを考えると、怒りの気持ちを抑制できます。
子どもの行動を先回りしてサポートしない
お子さまのことが心配でも、先回りする行為は避けましょう。おうちの方が常に先回りしていると、お子さまの主体性や自分で考える力が伸びません。子どもを待つ姿勢を大切にし、ゆったりと構えるようにします。
お子さまに行動を促したいときは、「お母さんは~したほうがいいと思うよ」など、自分を主語にして伝えましょう。弱い強制力で、やるべきことを伝えられます。
非認知能力を伸ばすためには習い事や家庭学習がおすすめ
お子さまの非認知能力を伸ばしたい場合、習い事や家庭学習を取り入れる方法があります。以下で非認知能力の養成につながる習い事や家庭学習について解説します。
非認知能力を伸ばせる習い事・家庭学習の選び方
非認知能力を伸ばす目的で習い事や家庭学習を選ぶ際は、次の3つのポイントに着目します。
- お子さまが興味を持っている
- お子さまのペースで取り組める
- 多様な体験ができる
興味・関心は、非認知能力の土台になります。何に興味があるかわからない場合は、複数の候補を見せてお子さまに決めてもらってもよいでしょう。
また、過度な競争がなく、お子さま自身のペースを大切にできる習い事を選びましょう。普段の生活ではなかなか取り組めない、多様な体験ができることを基準に選ぶと、お子さまの世界観を広げられます。
非認知能力の養成におすすめの習い事・家庭学習
非認知能力を伸ばす習い事・家庭学習は、以下がおすすめです。
- 英語
- プログラミング
- 水泳
- リトミック
特に英語は自宅でも学べるうえ、おうちの方も一緒に取り組めるため、コミュニケーションの時間になります。学習する過程で、楽しみながら学ぶ時間も、うまく発音できず悔しい思いをする時間も、どちらも非認知能力を育ててくれます。
まとめ
非認知能力は、数値化できない「心の力」です。これからの時代に欠かせない力であると注目されており、日常生活の中でも育める力です。
また、お子さまの非認知能力を養うためには、家庭学習もおすすめです。Sanrio English Masterは、親しみやすいキャラクターとともに、お子さまが無理なく楽しんで英語を学習できるため、お子さまが自主的に継続して取り組むことが期待できます。また、英語を学ぶ過程で達成感や自己肯定感をはじめとした非認知能力を育めます。
まずは無料サンプル・教材無料体験で、お試しください。