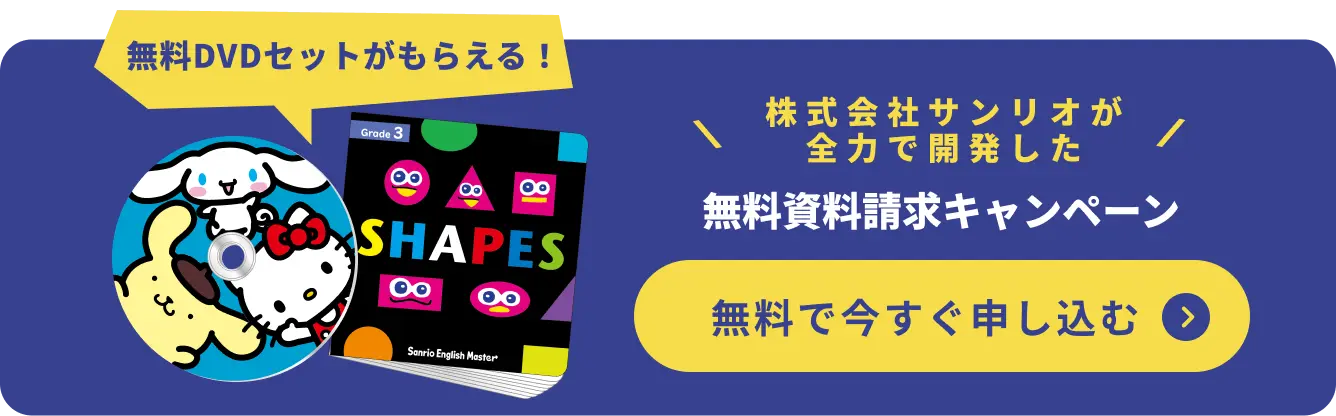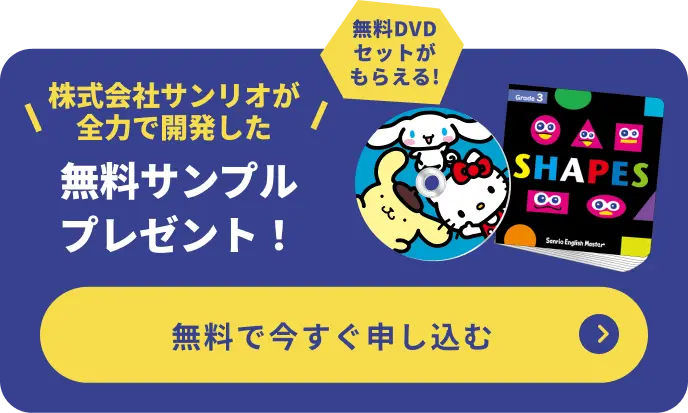リトミックのやり方とは?0歳からの年齢別ポイントや注意点を解説!

リトミックは、幼稚園・保育園のカリキュラムやお子さまの習い事として人気です。しかし、リトミックという名前は知っていても、やり方までは分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、リトミックの内容をはじめ、やり方や注意点について解説します。
目次
リトミックとは?
リトミックとは、音楽を使った教育法のひとつです。まずは、リトミックの要素や効果について紹介します。
リトミックとは教育法のひとつ
リトミックとは「ダルクローズ音楽教育法」とも呼ばれる教育方法です。音楽教育法として、楽器を演奏したり、音楽に合わせて身体を動かしたりして子どもの可能性を伸ばします。
リトミックの3要素
リトミックには、動き、ソルフェージュ、即興の3要素があります。動きとは、音楽を聴いて感じたことを動きで表現することです。ソルフェージュとは楽譜を読み、音楽を理解・表現すること、即興は自分で考えて表現することを指します。
リトミックの効果
リトミックの目的は、リズム感や音を聴き取る力などの音楽的能力を伸ばすことです。お子さまの潜在的な基礎能力である表現力、思考力、注意力、集中力、創造性なども育みます。複数人で行うリトミックは、アイコンタクトや動きのシンクロ、発表する経験などを通じてコミュニケーション能力を伸ばします。
リトミックのメリット
乳幼児期は自分の身体を上手にコントロールすることが難しい時期です。リトミックでは、音楽の変化に合わせて動くので、身体のコントロール能力を身につけられます。また、耳をすまして音楽を聴いたり、先生や友達の真似をしたりするなど、脳を使う場面が多く、知的感覚が向上するのもメリットです。
グループで行うリトミックは友達と協力する機会も多いため、コミュニケーションを通して社会性や協調性が身につきます。
リトミックのやり方は?リズム遊びとの違い
リズム遊びは、振り付け通りにダンスをしたり指導者の動きを真似たりするなど、音に対する動きや活動が決まっています。一方、リトミックは、音楽に合わせて自分のタイミングで体を動かすなどの表現を行うため、リズム遊びとは異なります。
リトミックの歴史
リトミックは、スイスの作曲家兼音楽教育家「エミール・ジャック=ダルクローズ」によって考案されました。当初は音楽を志す若者を対象としていましたが、次第に子ども向けにシフトしていき、近年は幼稚園や保育園でも取り入れられています。また、大手音楽教室やピアノ教室、幼児教室などで習い事としてのレッスンが展開されています。
リトミックのやり方
リトミックといっても、以下のようにさまざまなやり方があります。それぞれの特徴や参考動画をチェックしてみましょう。
即時反応
即時反応とは、音楽が流れている間は動いて、音楽が止まったら体の動きも止める活動です。音楽をよく聴き、素早く反応することで集中力を鍛えます。
※参考:【Step3 Lesson「だいくさん」】|リトミック研究センター【公式チャンネル】
手遊び歌
手遊び歌は、音楽に合わせて手や指を動かしてリズム感を育みます。手と指を動かすと、脳に刺激を与えられる点もメリットです。代表的な手遊び歌に「Under the Spreading Chestnut Tree」があります。日本でも「大きな栗の木の下で」として親しまれている歌です。
歌詞にいくつかのバージョンがありますが、曲自体はおうちの方もお子さまも知っている場合が多いので、一緒に楽しめるでしょう。「If You‘re Happy and You Know It」は、日本でも有名な「幸せなら手をたたこう」という手遊び歌の英語バージョンです。「手をたたく」動作を入れて、親子で楽しく歌いましょう。
ダイナミクス
ダイナミクスは音の強弱を表します。音の強弱や大小、だんだん大きくなったり小さくなったりする表現がダイナミクスの特徴です。例えば、軽やかな音でウサギ、大きくてゆっくりした音で象などの表現ができるようになります。
※参考:【親子リトミックりとりと】0才から3才の親子リトミック秋のレッスンをご紹介|音楽教室クレール
ビート・拍子
ビートは「拍」とも呼ばれ、心臓の鼓動のように音楽のなかで、常に一定に刻まれる基本的なリズムを指します。一方、拍子とは、強拍と弱拍が繰り返されることで生まれるリズムのまとまりのことです。まずはビートを感じ取ることから始め、次第に拍子の違いを意識できるようになると、より深くリズムを理解できるでしょう。
参考:【Step4「拍と数」】|リトミック研究センター【公式チャンネル】
長調・短調や高低の聴き分け
長調・短調や高低を学ぶのもリトミックの重要なポイントです。一般的に、長調は明るく、短調は暗く聴こえるため、長調・短調を聴き分けてどのような気持ちかを表現します。高い音は手を挙げる、低い音は手を床につくなどの動作をつけると集中力や瞬発力を高められます。
リトミックを効果的に行う年齢別のやり方
リトミックは、自分で体を動かせない0歳児からでもできます。何歳までに始めなければならないということもありません。リトミックを展開する教室では、表現力や創造力が発達中の0歳~6歳を対象にしている傾向があります。リトミックを効果的に行う年齢別のやり方は以下のとおりです。
0歳児
基本的には、首が座る生後4~5か月程度の時期から始めることが多いようです。0歳児のリトミックは具体的に以下のように行います。
- 即時反応:音を鳴らす、止める
- ビート:早いビート、遅いビートを意識して音を鳴らす
- ダイナミクス:ハンカチやスカーフを振る、体をさわる
1歳児
1歳児のリトミックは具体的に以下のように行います。
- 即時反応:音に合わせて歩く・止まる、ボールを転がす・止める
- ビート・拍子:言葉に合わせて手を叩く
- ダイナミクス:音に合わせて動物の真似をする
2歳~3歳児
2~3歳児は、音の強弱やテンポの速い・遅いなどが分かるようになる時期です。音に合わせてハンカチを振ったり、上下に動かしたりするやり方がおすすめです。また、人の観察や真似が上手になる時期でもあります。音に合わせたごっこ遊びや、動物や魚になる、電車になるなどのものまね遊びも有効です。
身体機能が成長して、走りたい、動きたいなどの気持ちも生まれるようになります。歩く・走る・スキップする・止まるを組み合わせたやり方もよいでしょう。音に合わせて動きを止めるとエネルギーを抑えることも学べます。
4歳~5歳児
4~5歳になると、しゃがんだ状態から「ドレミファソラシド」に合わせて立ち上がるなど、より繊細で複雑な動きが表現できるようになります。また「楽しい」「悲しい」といった感情を、長調や短調の違いを聴き分けながら表現する様子も見えはじめます。この時期は、友達と協力する力も育ってくるため、グループで発表する機会を設けるのもよいでしょう。
リトミックのやり方のポイント
親子ともにリトミックを楽しく行うには、以下のようにやり方のポイントを押さえることをおすすめします。
はじめは1つから
できることを1つずつ増やしていくのがポイントです。1つの課題がクリアできたら、ダイナミクスとリズムを組み合わせるなど、難易度を少しずつ上げていきましょう。
目的を持って行う
リトミックを行う目的を事前に明確にしておくことが大切です。目的が明確ではないと、どのような演奏の仕方をすればよいか分からなくなります。
見本を見せる
慣れないうちは、やり方が分からなくて戸惑うお子さまもいます。指導者やおうちの方が楽しく表現する姿を手本として見せ、興味を引き出すことが大切です。
お子さまの表現を尊重する
意図と異なる動きや、ほかのお子さまと違う動きをしても否定しないことが重要です。音楽を使った自由な表現が大切なので、お子さまなりの感じ方を尊重しましょう。
リトミックを行う際の注意点
リトミックを行う際は、以下の2点を常に心に留めておくことが大切です。
正解がないことを理解しておく
リトミックには正解はないため、感じるままに自由に動いたり歌ったりしても問題ありません。これという決まりはないので、自己表現することを基本とした活動を検討しましょう。
お子さまに無理強いしない
リトミックは、すべてのお子さまが興味を抱いたり楽しんだりできるとは限りません。また、はじめは上手にできなくても、回を重ねるごとに楽しさを感じながらできるケースもあります。もし興味を示さなかったり、嫌がったりする様子が見られた場合でも、無理に続けさせるのではなく、お子さまの気持ちを大切にして見守ることが重要です。
自宅学習ならSanrio English Masterがおすすめ
Sanrio English Masterは、リトミックに使用できる手遊び歌や童謡が入っています。童謡にはハローキティやシナモロールなど、みなさんが知っているおなじみのサンリオキャラが大集合しているため、お子さまと一緒に楽しめるでしょう。
0歳から8歳まで学べる充実したカリキュラムになっており、1レッスンあたり20分の動画で、見る・聞く・体を動かすなど、五感を使って楽しく学べる内容です。動画以外にも、お子さまが夢中になる絵本や知育玩具で自然と発話を促すため、高度な英語表現が身につきます。
親子で楽しめるコンテンツで知育につながるSanrio English Masterを、ぜひ無料サンプルでお試しください。
まとめ
リトミックは、音楽を通じて子どもの表現力やリズム感を育む教育法です。音楽に合わせた動きや即興表現を取り入れることで、思考力や創造力の発達も促します。年齢に応じた方法を取り入れると、より効果的に楽しめます。無理に取り組ませるのではなく、自由な表現を大切にすることがポイントです。
Sanrio English Masterは、自宅にいながら親子で楽しみつつ学べる0~8歳向けのAll English教材です。リトミックにも活用できる「Under the Spreading Chestnut Tree」や、「If You‘re Happy and You Know It」などの手遊び歌や童謡も入っています。無料サンプルや教材体験もあるので、まずはお子さまと一緒にそこから始めてみてください。