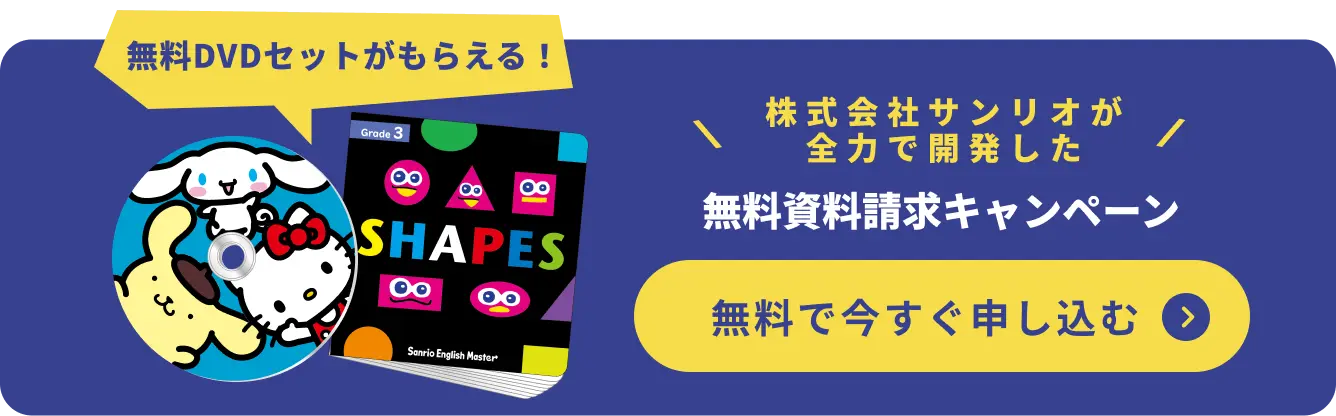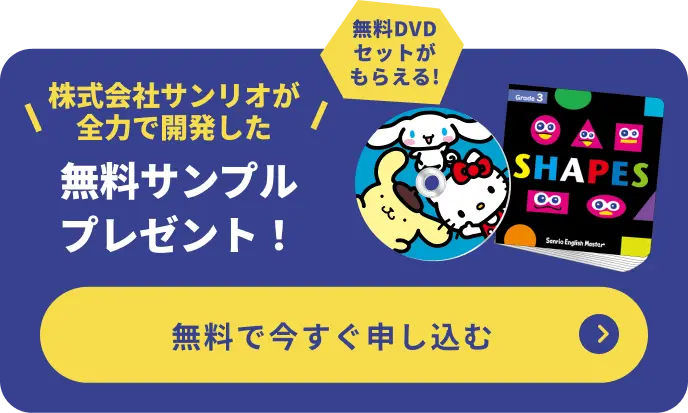STEAM教育とはどういうもの?特徴や推進される背景などを解説

「STEAM教育」という言葉を聞く機会が増えたものの、その単語からはどのようなものか分かりにくいという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、STEAM教育の基本情報から特徴、推進される背景などを解説しています。お子さまへの教育に、STEAM教育を活用してみたいと考えている人は参考にしてください。
目次
STEAM教育とはどういうもの?
STEAMとは、Science:科学、Technology:技術、Engineering:工学、Arts:芸術、Mathematics:数学という5つの単語の頭文字を組み合わせたものです。
STEAM教育とは、これら5つの分野を統合的に学ぶ教育のことを指します。この教育を通じ、技術革新による人工知能の影響拡大を受け、IT社会に順応した人材の育成を目指しています。
STEAM教育を構成する5科目
STEAM教育が5つの分野であることは分かったものの、それぞれの科目の中身は具体的にどのような内容なのでしょうか。
それぞれの科目ごとに、どのような内容を学ぶのかを解説します。
S(Science):科学
STEAM教育におけるS(Science)とは、自然現象をはじめとする科学の分野を指します。具体的な範囲は人体や元素、植物、動物などをはじめ、ごく身近な世界に関する原理から宇宙まで、多岐にわたります。中学校では光の屈折や反射、高校では太陽光や電磁波などを学びます。
子どもに物事に対する好奇心を抱かせるための役割があり、数理的思考の土台を養います。
T(Technology):技術
STEAM教育におけるT(Technology)とは、科学をもとに実際にものを作る技術を指します。具体的には小中学校で必修となっているプログラミング、材料と加工の技術、エネルギー変換の技術などの範囲です。
プログラミングをはじめとする学習により、論理的思考力や課題解決力を養います。また、地道な作業が必要なため、ストレスへの耐性や根気などを養うことにもつながるでしょう。発想力の育成により、キャリアの選択肢増加が期待されます。
E(Engineering):工学
STEAM教育におけるE(Engineering)とは、社会に役立つものや仕組みを作るための知識や能力を身につけることです。具体的には、プログラミングして自走可能なロボットを製作したり、設計図や電子回路を作成したりします。
知識をものづくりに活用し、生産力や空間把握能力を養うことが目的です。近年では、小学生でも安全に制作できるロボットキットが開発されているため、STEAM教育においても活用されています。
A(Arts):芸術
STEAM教育におけるA(Arts)とは、ダンスや演劇・音楽・絵画・デザインなど一般的に芸術とされる分野をはじめ、文化・生活・経済・法律・政治などを含む広い範囲を指します。
自身のアイデアを具現化するための発想力や創造力を得るために、思いや考えを表現する力や伝える力を養います。
M(Mathematics):数学
STEAM教育におけるM(Mathematics)とは、計算や図形など数学の分野を指すものです。高校では、データの相関や微分積分なども学びます。公式をはじめとする法則を学び、問題を解くことで、論理的思考力を養います。
論理的思考力が身につくと、STEAM教育での他の科目にも役立つでしょう。
STEAM教育が推進される背景
日本政府が2016年に「Society 5.0」を発表したことで、日本でSTEAM教育が推進されるようになりました。Society 5.0とは、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによって、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のことです。
そのような社会を生き抜くには各教科の知識をもとに、さまざまな情報を統合し課題を発見・解決する能力が求められます。その能力を身につけるにはSTEAM教育が有効なため、推進されているという背景があります。
STEAM教育の歴史
STEAM教育は、科学・技術・工学・数学を学習する「STEM教育」が前身です。STEM教育は、理系人材の育成を目的に1990年代のアメリカで提唱され、2009年当時のオバマ大統領が演説でその重要性を語ったことで、注目されるようになりました。その後、創造力を伸ばす「芸術(Arts)」が追加され、STEAM教育となりました。
STEAM教育の課題
考える力を養うSTEAM教育に注目が集まっているものの、現時点では複数の課題が解決されていないという状況があります。
STEAM教育における、おもな4つの課題を解説します。
教員が不足している
STEAM教育の知識を有し、子どもの探究心を刺激するように教えられる教員は不足しています。教員の業務量は多く、教員自体が不足しているため日常的な業務だけで多忙です。加えて、小中学校ではプログラミング教育が必修となり、新たな専門性が求められています。STEAM教育の十分な知識を得るだけの時間の確保が、難しいという状況があります。
環境整備が遅れている
STEAM教育において、ICTの活用は欠かせません。自身の課題を探究したり、友人同士で考えを共有したりする必要があるためです。それを解決すべく、文部科学省の「GIGAスクール構想」によって、生徒1人につき1台の端末とネットワーク環境が整備されています。
ただし、端末が故障したり、通信速度が遅かったりと問題が発生することも考えられるでしょう。引き続き、環境の整備が求められています。
理数科目に苦手意識のある生徒が多い
STEAM教育の多くは、理数系の科目です。それらの科目を楽しめることが重要ですが、日本の子どもは世界と比べて、理数科目を楽しいと感じている生徒が少ないとされています。生徒が理数科目に対し、楽しさを感じられるような授業が求められています。
家庭や地域によって教育の差が生じやすい
STEAM教育に使用する機器は高額のものが多く、家庭や地域によって教育の差が生じやすい状況です。たとえば、家庭のインターネット環境や自治体の取り組みの有無、公立か私立かなどによります。
STEAM教育は考える力を伸ばすもので、eラーニングを活用すれば授業だけでなく自宅でも学習できます。家庭や地域の差がなく、どこからでも使えるようにすることが必要です。
日本におけるSTEAM教育の実例
具体的に、日本ではどのようなSTEAM教育が実施されているのでしょうか。3つの実例を解説します。
STEAMライブラリー
STEAMライブラリーとは、経済産業省が無料で公開しているデジタルコンテンツライブラリーです。民間事業者や高校・大学・研究機関などが参画しており、小中学校や高校での学習で自由に利用できます。
子どもたちが自身で、いつでも視聴・活用することが可能です。幅広い社会的・学問的テーマについての、動画や資料が公開されています。学習指導要領と紐づけられているため、学習に使用しやすいでしょう。
科学の甲子園
科学の甲子園とは、高校生がチームを組み、理科・数学・情報の複数分野で競う大会です。国立研究開発法人科学技術振興機構が創設し、2011年度にスタートしました。全国大会では6人1チームの筆記競技と、3~4人1チームの実技競技が実施されます。科学好きを増やすと同時に、トップ層を伸ばすべく開催されています。
STEAM教育実践モデル校事業
STEAM教育実践モデル校事業とは、2020~2022年度に兵庫県が実施した事業です。STEAM教育の推進や、国内外で活躍できる「未来を創造する力」を備えた人材の育成が目的です。2022年以降には、兵庫県以外でもSTEAM教育推進事業が開始されています。
海外におけるSTEAM教育の実例
もちろん、STEAM教育は海外でも実施されています。アメリカとシンガポールにおける、2つの実例を解説します。
High Tech High
High Tech Highとは、STEAM教育を実践するアメリカ・カリフォルニア州の学校です。High Tech Highではプログラミングや非認知能力の向上、自分自身で考え実現する力を養うことに力を入れています。また、eラーニングを積極的に取り入れています。授業料は無料で、教科書や成績表はありません。
サイエンスセンター
サイエンスセンターとは、1977年に開設されたシンガポール政府直属の人材育成機関です。STEAM関連領域に関してスペシャリストが授業を実施し、全中学生にSTEAMプログラムを提供しています。修士号や博士号を有するスペシャリストが、それぞれの学校で授業を実施しています。
まとめ
IT社会に順応した人材の育成を目指し、数理的思考を養う5つの分野を統合的に学ぶSTEAM教育が、国内外で推進されています。日本では2016年頃より推進されるようになりました。課題もあるものの、子どもの教育に活用されるシーンが増加しています。
お子さまの自立心や集中力を向上させたいと考えているのであれば、Sanrio English Masterをぜひご活用ください。株式会社サンリオが提供する子ども向け英語教材で、可愛らしいキャラクターが多く登場します。お子さまが楽しく学べる設計で、遊びながら自然と英語や知育に取り組めます。