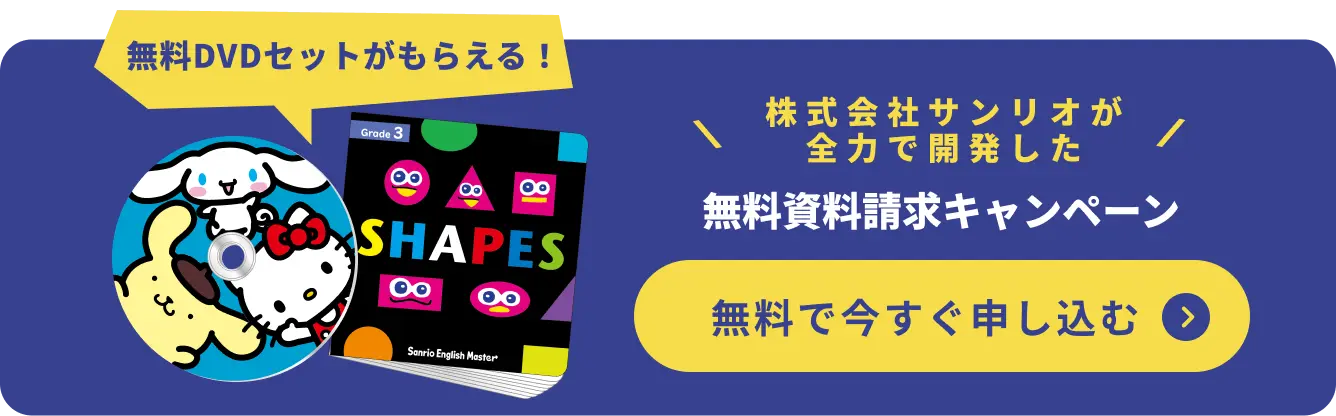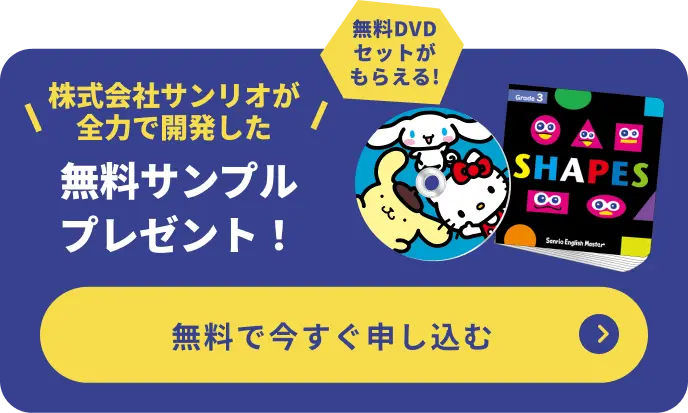子どもの知的好奇心を刺激する方法とは|保護者が注意すべきポイントも解説

お子さまの健やかな成長のためにも、知的好奇心を刺激することは重要です。周りの大人たちが適切にサポートすれば、お子さまの知的好奇心をより育みやすくなるでしょう。
本記事では、お子さまの知的好奇心を刺激する方法や、知的好奇心を高める上でおうちの方が注意するべきポイントを解説します。
目次
知的好奇心とは
知的好奇心とは、物事を「もっと知りたい」と思う気持ちのことです。
分野を問わず未知のものすべてに対する興味を、一般的に「好奇心」と呼びます。知的好奇心はそのなかでも、特に科学や歴史といった知的な分野に対する好奇心を指します。
知的好奇心は、子どもの健やかな成長にとって不可欠なものです。子どもの知的好奇心を刺激しながら育ててあげることは、保護者の大切な役割のひとつといえるでしょう。
知的好奇心には2つの種類がある
知的好奇心には、大きく分けて2つの種類があります。ここでは、拡散的好奇心と特殊的好奇心の違いについて解説します。
「未知のものを広く知りたい」拡散的好奇心
拡散的好奇心は、未知の物事や情報を幅広く知りたいという気持ちです。ジャンルにはあまりこだわらず、新しい刺激を求めてさまざまなものに興味を持つ特徴があります。
例えば、分野にとらわれず手あたり次第に本を読んだり、特に目的がなくてもインターネットを見たりする行動は、拡散的好奇心によるものといえます。「とにかくいろいろなことを知りたい」という気持ちが強い子どもは、このタイプの好奇心が旺盛です。
「ひとつのことを深く知りたい」特殊的好奇心
特殊的好奇心は、興味を持ったことを深く知りたいという気持ちです。あてもなく情報を調べるのではなく、何らかの目的を持って探索行動をする特徴があります。
特殊的好奇心の例として、見聞きした情報の真偽を確かめるために専門の本で詳しく調べたり、日常生活で疑問に思った現象を深く掘り下げたりする行動が挙げられます。
「一度興味を持ったことにのめり込む」「事象の根拠を理解したい」と思う子どもは、このタイプの好奇心が強い傾向があります。
子どもの知的好奇心を刺激するメリット
子どもの知的好奇心を刺激すると、学習や成長においてさまざまなメリットがあります。
学習への意欲が高くなる
知的好奇心が刺激されると、子どもは指示されなくても自ら学習する姿勢を持ちます。この意欲は子どもの心の内から湧き上がってくる内的な動機なので、ごほうびなどの外的な動機で行う学習よりも、モチベーションを維持しやすくなります。
授業で習ったことに興味を持ち、「もっと知りたい」と自発的に本を読んだり、先生に質問したりする行動も増えるでしょう。
課題発見能力が身に付く
子どもが成長して社会人になると、自分で考えて問題を解決する力が問われます。適切に問題を解決するには、前提として正しく課題を発見することが重要です。
子どもの頃から知的好奇心が高いと、日常のなかでさまざまな疑問を持ち、物事の本質を捉えようとする思考が身に付きます。その結果、着目すべきポイントを探す力が高くなる傾向にあります。
主体的に行動ができるようになる
知的好奇心が高いと、学習だけでなく、学校行事や日常生活でも主体的に行動できるようになります。未知の体験に対する抵抗が少なく、失敗を恐れすぎずにチャレンジできるようになるでしょう。
「知らないことを知る」「やったことのないことをする」といった経験自体を好きになるため、物事への主体性が向上します。
さまざまな価値観を受け入れやすくなる
さまざまな分野に関心を持って情報に触れていると、世界には多様な価値観があることを自然と知っていきます。
小さな頃から多くのジャンルに触れることで視野が広がり、多面的に物事を捉えられるようになるでしょう。自分と属性の違う人に出会っても、価値観の違いをポジティブに受け入れやすくなります。
知的好奇心が低いと子どもにどのような影響がある?
知的好奇心が低いと興味が湧きにくくなり、行動の幅が狭まることがあります。ここでは、知的好奇心の低さがもたらす影響を解説します。
変化や新しい刺激を避けがちになる
知的好奇心が低い子どもは「いつもの環境」に安心感を覚え、変化や新しい刺激を避ける傾向があります。家にこもって外出が少なくなり、行動力もなくなりがちです。
他者への関心を持ちにくくなる
「知らないことを知りたい」という欲求が低いため、他人の考えや自分とは異なる価値観に興味を持ちにくくなるでしょう。学習に対しても受動的になりがちで、保護者などの大人から指示されない限り勉強をしなくなる可能性もあります。
ストレスを溜め込みやすくなる
周りの大人から指示されて嫌々学習していると、学校生活や勉強にストレスを感じる場合があります。興味の幅が狭いために退屈に感じる時間が長く、他人への関心の薄さから、子ども同士の人間関係でストレスを溜めてしまう可能性もあります。
子どもの知的好奇心を刺激する方法
子どもの知的好奇心を刺激するには、環境を整える工夫が大切です。ここでは、知的好奇心を高める方法の例を紹介します。
目立つ場所に図鑑や地球儀などを置く
日常生活のなかで、自然と知的好奇心が湧くような仕掛けをつくりましょう。お子さまの目に入りやすい場所に、図鑑や地球儀などの調べ物ができるアイテムを置くと効果的です。
さまざまな情報が流れてくる場所に置いておけば、疑問を持ったときにすぐ調べられるため、より効果が高まるでしょう。例えば、テレビの脇に地球儀や世界地図を置くことで、番組内で知らない国の名前が出てきたとき、すぐにどこにあるのかを探せます。
お子さまの関心に応じた場所に連れて行く
おうちの方が「この分野に興味を持ってほしい」と思っていても、お子さま自身に関心がなければなかなかうまくいきません。無理に興味を持たせようとするのではなく、お子さまが関心を持っている分野に応じて好奇心を満たすことが大切です。
例えば、動物が好きなら動物園、科学に興味があるなら博物館、自然が好きなら山や海などのスポットに連れて行くとよいでしょう。「知ること・学ぶことが楽しい」と感じると、別のジャンルにも興味を持ちやすくなります。
大人も学びを楽しむ
お子さまと接していて、「口癖が自分に似てきた」「昔の自分と同じ行動をしている」などと、感じたことはないでしょうか。
子どもは保護者をはじめとした大人の行動をよく観察しているため、保護者自身が楽しんでいる物事に自然と興味を持ちます。おうちの方が心から学びを楽しんでいれば、お子さまも学びを楽しむようになりやすいでしょう。
同じ本棚に大人向けの本と子ども向けの本を並べておき、おうちの方が日常的に読書する姿を見せるだけでも、お子さまの学びに対する興味を引き出せるかもしれません。
さまざまな人に会う機会をつくる
人はそれぞれ異なる考え方を持っています。親戚の集まりや習い事、地域のイベントなど、多くの人と触れ合う機会があれば、自然とさまざまな価値観に出会い、知的好奇心が刺激されるでしょう。
おうちの方が詳しくない分野について、他の大人が教えてくれることもあります。子どもの頃からたくさんの人と接することで考え方が柔軟になりやすく、対人関係で過剰なストレスを感じにくくなるでしょう。
お手伝いをしてもらう
家事のお手伝いも、子どもにとっては新しい刺激や発見の場になります。
例えば、料理では食材の名前や調理方法を学べます。洗濯や掃除を通じて、道具の使い方や生活の工夫を知る機会にもなるでしょう。ペットのお世話から、動物の習性を学ぶこともできます。
何となく手伝わせるのではなく、目的を持って家族の一員としての役割を与えることがポイントです。安全面に十分注意して、お子さまが楽しく学べる環境を整えましょう。
知的好奇心を育てるために保護者が注意するべきポイント
子どもの知的好奇心を刺激するためには、保護者の接し方が重要です。好奇心を削いでしまわないよう、注意すべきポイントを解説します。
お子さまが自分で考えるよう促す
大人なら簡単に分かることでも、すぐに答えを教えてしまうと、子どもは自分で考える習慣を身に付けにくくなります。
「なんでそう思うの?」と聞き返して考えを深めるよう促したり、「図鑑で調べられるかもしれないね」とヒントを出したりして、自分で解決できるように導いてあげましょう。
お子さまの興味や疑問を否定しない
お子さまの興味や疑問に対して、「そんなことどうでもいい」と突き放したり、「忙しいから後にして」と他のことを優先したりすると、質問する意欲自体を削いでしまう可能性があります。
仕事や家事をしている最中だったり、家を出なければならない時間が迫っていたりと、生活のなかにはさまざまな事情があります。しかし、タイミングを逃すとお子さまの好奇心は薄れ、興味を失ってしまいます。
できればその場で向き合い、質問に答えたり一緒に調べたりする時間を大切にしましょう。
お子さまの行動を制限しすぎない
子どもが何かに熱中しているとき、脳は活発に動いています。
大人から見ると意味が分からないと思える遊びでも、子どもにとっては新しい発見につながる大切な時間です。危険性がない限り、そっと見守って自由に試行錯誤させてあげましょう。
知的好奇心を刺激したいなら、やりたくない学習の押し付けも逆効果につながります。お子さま自身の興味による行動を尊重しましょう。
知的好奇心を刺激する教材の活用もおすすめ
知的好奇心を刺激するには、教材の活用も効果的です。遊びながら学べる教材を選べば、楽しみながら新しい知識を吸収できるでしょう。お子さまだけでなく、おうちの方も楽しんで取り組めるものがベストです。
Sanrio English Masterは、遊びながら英語を身に付けられる、0~8歳向けのAll English教材です。お子さまの発達段階に合わせて興味を持ってもらいやすいテーマを採用し、知的好奇心を刺激して疑問を持つ力や自分で考える力を養います。
身体を動かしたり遊んだりしながら学べるため、楽しんで続けやすいこともポイントです。
まとめ
お子さまの知的好奇心を刺激するには、おうちの方の接し方や日常生活の工夫が重要です。教材も活用して、「楽しい」「もっと知りたい」と思えることを増やしてあげましょう。
Sanrio English Masterのメイン教材であるDVDの動画には、お子さまの知的好奇心を引き出すテーマを盛り込んでいます。
例えばStage2のアニメ回では、「どうして雨は降るの?」「どうしてキリンは首が長いの?」「どうして鳥は飛べるの?」といった大人でも答えにくい疑問に対して、キャラクターのエディたちと一緒に冒険して好奇心を育みます。
今なら無料DVDセットにこちらの内容が含まれていますので、ぜひお申し込みください。