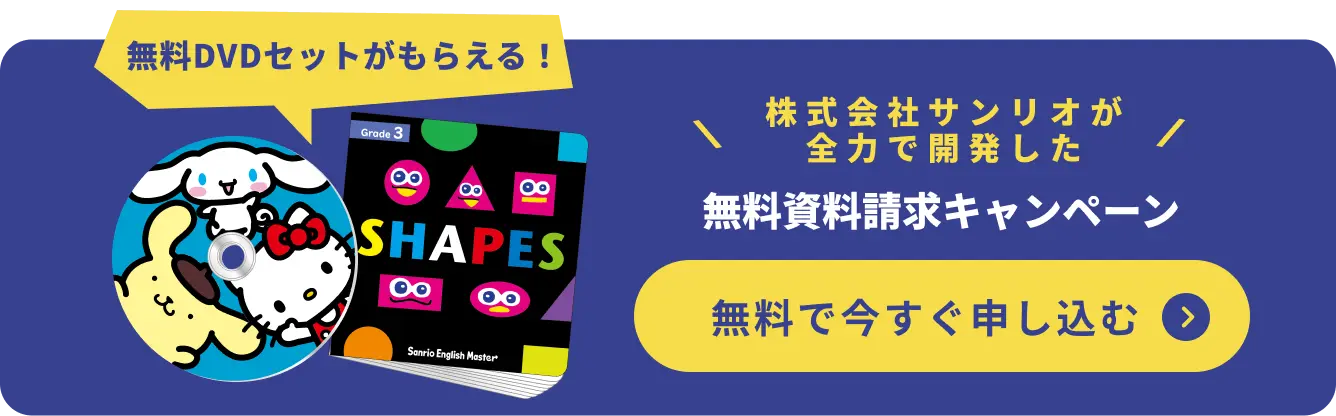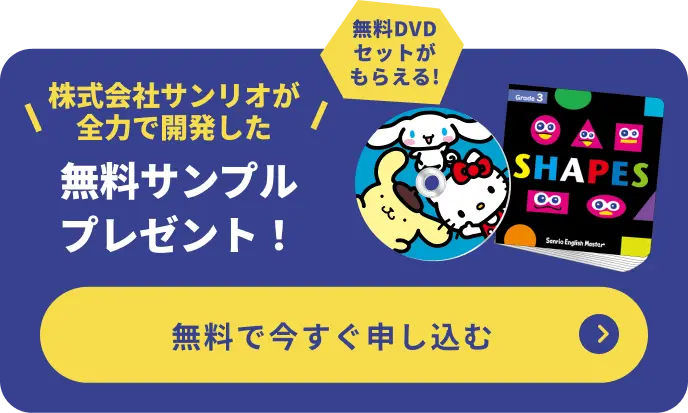三歳児神話とは?根拠はない?子どもとの向き合い方や集団保育のメリットも解説

日本では、子どもの発達に関して「三歳児神話」というものがあります。子どもの健やかな成長を願うおうちの方にとって、三歳児神話はしばしば不安の種となります。では、三歳児神話に科学的な根拠はあるのでしょうか?
本記事では、三歳児神話はどのようなもので、なにを根拠としているのか解説します。家族みんなが無理なく過ごすための向き合い方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
三歳児神話とは?
三歳児神話とは、「子どもの発達のことを考えるなら、子どもが三歳になるまで母親は家庭にいて、子育てに専念するべき」とする考え方です。
日本では、比較的古くからこの三歳児神話が信じられており、世代を超えて広く知られています。
三歳児神話がおうちの方に与える影響
以前の日本では、父親が働きに出て母親が家庭を守るというスタイルが一般的でしたが、現代は共働きの家庭が増えています。そのようななかで、共働きの必要性を感じつつも、三歳未満のお子さまを保育所や幼稚園に預けてよいものか悩んでしまう方は多いものです。
また、自分の親世代(子どもの祖父母世代)から「まだ小さいのに保育所や幼稚園に預けて大丈夫なの?」といった言葉を投げかけられ、迷いが生じてしまうケースも多いでしょう。
しかし、家庭のあり方や子育てに絶対的な正解はありません。こうした言説に振り回されず、各家庭やお子さまの個性に合わせた育児を実践することが重要といえます。
【根拠はない?】三歳児神話が生まれた背景
そもそもなぜ、三歳児神話が生まれたのでしょうか?
三歳児神話が生まれた背景や、根拠について解説します。
三歳児神話が生まれたきっかけ
三歳児神話のもととなったものは、1951年にイギリスの精神医学者であるジョン・ボウルビィが作成した報告書だとされています。
WHO(世界保健機関)からの依頼を受けたボウルビィは、孤児院で暮らす子どもや、家族と別々に暮らしたことのある子どもの心身の発達に遅れが生じることが多い理由を検討し、その要因として「三歳までの母性的養育の剥奪」を挙げました。そしてボウルビィは、「三歳までに最低でも一人の養育者と心理的な結びつきを育むことが、子どもの発達には重要である」と提唱しました。これを愛着理論といいます。
「母性的養育」は必ずしも「母親による養育」を意味するものではありませんが、日本ではこの解釈が広まった結果、「三歳になるまで母親は子育てに専念すべき」という説が生まれました。以前の日本社会では、父親が外に出て働き、母親が家庭を守るという家庭のあり方が一般的だったため、こうした説が受け入れられやすかったのではないかと考えられています。
日本の三歳児神話は誤り?
人間の脳の発達は乳幼児期に急速に進み、三歳になるまでにはほとんど完了することが分かっています。そのため、三歳までの過ごし方が、子どもの発達に影響すること自体は誤りとはいえません。
しかし、近年の研究では、子どもが三歳未満のときに母親が就労しても、子どもの発達には影響を及ぼさないという結果が得られています。
日本における三歳児神話は、もともと「母性的養育」が母親との関係に限ったものであると誤って広まったものであり、少なくとも「三歳になるまでは母親が子育てに専念すべき」とする説には根拠がないと考えられるでしょう。
日本以外でも三歳児神話と同じ考え方はある?
スウェーデンでは、子どもが一歳になるまでは家庭内で育てることが重要と考える「一歳児神話」が広く知られています。そのため、スウェーデンでは赤ちゃんが生まれた家庭に対して480日の育休が保証されており、父母がそれぞれ240日ずつ育休を取得することを推奨しています。その代わり、日本のように0歳児を預けられる保育サービスはありません。
ただし、スウェーデンにこのような制度があるのは、国が0歳児を預けられる施設を整備するよりも、父母の有給取得に予算をかける方に合理性を見出した結果でもあります。また、母親だけでなく父親も育児に関わるべきとされており、日本の三歳児神話とは少し違っています。
三歳までのお子さまを預けるメリット
三歳児神話には根拠がないことをお伝えしてきましたが、「可能なら三歳くらいまで自宅保育をした方が、子どものためにはよいのでは?」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、三歳までのお子さまを保育所・幼稚園に通わせることには、次のようなメリットがあります。
社会性が高まる
子どもは、保育所・幼稚園でお友だちと集団生活を送るなかで、他者とのコミュニケーション方法を学んでいきます。
さまざまなタイプの子どもたちや先生、近隣の人たちとの関わりを通じて、早期から社会性を身につけることが可能です。
自分でできることが増える
保育所や幼稚園では、低年齢の子どもにも、できる範囲で自分のことは自分でしてもらうようにすることが多いものです。
そのため、保育所や幼稚園に通い始めると自分でできることが増えます。すると、お子さまの自信が育まれ、ものごとに積極的に取り組めるようになります。
さまざまな経験ができる
砂場遊びやお遊戯など、自宅ではなかなかできない経験ができることも、保育所や幼稚園に預けるメリットです。
異なる年齢の子と一緒に遊んだり、チームで活動したりとお友だちと協力する機会も多く、思いやりの気持ちが育まれます。
三歳までの発達の特徴
三歳までの子どもの発達の特徴は、以下の通りです。
乳児期(~一歳未満)
「心理社会的発達理論」では、一歳未満の子どもを「乳児期」と位置付けています。これは発達心理学者の、エリク・ホーンブルガー・エリクソンが提唱したものです。
エリクソンによると子どもの発達には8つの段階があり、そのうちの最初の段階である乳児期は、母親やそれに近い存在の人との関わりを通じて、世界に対して安心感を得る時期です。
信頼できる人からの愛情を受けて、基本的信頼感を獲得していきます。
幼児前期(一歳~三歳)
エリクソンは、一歳から三歳までを幼児前期に分類しています。
幼児前期は言語領域の発達が著しく、子どものなかで自律心が生まれる時期です。なんでも「自分でやる」と言うようになったり、周囲の大人と同じことをしたがったりする子も多いでしょう。
三歳までは、周囲との信頼感を育む時期
愛着理論に基づいても、三歳までの周囲との関わり方は基本的信頼感の形成に大きな影響を与えるといえます。
基本的信頼感とは、「自分はあるがままいるだけで価値があり、大切にされている存在なんだ」「自分には守られて、安全に過ごせる場所がある」という、周囲に対する絶対的な信頼感のことです。
三歳までの時期におうちの方や保育所・幼稚園の先生など、愛着関係にある人と信頼関係を育むことが健全な発達を促し、お子さまの幸福度にも影響を与えます。
子どもに「自分は愛されている」という実感を持ってもらえるよう、周囲の大人が十分な愛情を注ぐことが大切です。
自宅保育と保育所・幼稚園で、子どもの発達に差は出る?
三歳児神話のような子どもの発達に関する言説が気になるのは、ひとえに子どもの将来を思うからこそ。
では、自宅でお世話をする場合と保育所や幼稚園に預ける場合とで、子どもの発達に違いが生じることはあるのでしょうか?
差が生じると証明することはできない
結論からいうと、自宅保育の子どもと、保育所・幼稚園に通っている子どもの間で、発達において有意な差があると言い切ることはできません。なぜなら、子どもはさまざまなものごとから影響を受け成長していき、「家庭で過ごしたかどうか」だけがすべてではないためです。
また、自宅保育と保育所・幼稚園にはメリット・デメリットがあるので、それぞれの家庭の状況に応じて選択することが重要となります。
一緒に過ごす時間の長さよりも関わり方が重要
1990年代にアメリカで行われた研究では、母親と子どもの愛着の質は、保育所や幼稚園に預けるタイミングや時間などに左右されないという結果が分かりました。
この研究結果からみても、子どもの健やかな発達には、母親が一緒に過ごす時間の多さよりも、愛情を言葉で伝えたり、スキンシップをとったりといったコミュニケーションの影響度が大きいと考えられます。
※参考:保育の質と子どもの発達:アメリカ国立子ども人間発達研究所の長期追跡研究
三歳児神話に対する向き合い方
今まさに三歳未満のお子さまを育てている方は、三歳児神話とどのように向き合えばよいのでしょうか?
一般的な考え方に囚われすぎない
三歳児神話はあくまで神話であり、日本では間違った形で広まってしまったという背景もあります。
三歳児神話に限った話ではありませんが、特定の考え方に囚われすぎず、お子さまに合わせた子育てを実践することが大切です。
「家族みんなが心地よく過ごせること」も大切に
お子さまだけでなく、家族みんなが心地よく過ごせる育児スタイルを確立することも重要です。
「子どものため」とおうちの方が無理をしてストレスをため込むと、イライラしている気持ちがお子さまに伝わってしまいます。すると、お子さまがおうちの方の顔色をうかがうようになり、自分の感情を素直に伝えられなくなってしまう恐れもあるでしょう。
三歳までのお子さまを預けてよいか迷ったときの対処法
仕事に復帰はしたいけれど、三歳に満たない子を預けることに不安を感じている人に向けて、おすすめの対処法を紹介します。
信頼できる保育所・幼稚園を選ぶ
信頼できる保育所・幼稚園を選ぶことが、不安の軽減につながります。
先生の雰囲気や教育方針、安全性などをチェックし、お子さまが安心して過ごせる施設を選びましょう。また、保育所や幼稚園の先生とコミュニケーションをとり、「普段はこういうふうに過ごしていますよ」「こんなことができるようになりました」といった日々の様子を教えてもらうとよいでしょう。
自宅保育と集団保育のメリット・デメリットを比較する
集団保育のメリットについては前述の通りですが、自宅保育と集団保育にはそれぞれメリット・デメリットがあります。一概にどちらがよいと言い切れるものではなく、お子さまの個性に合わせて選ぶことが大切です。
以下に、自宅保育と集団保育のメリット・デメリットをまとめました。
|
|
メリット |
デメリット |
|
自宅保育 |
|
|
|
集団保育 |
|
|
まとめ
三歳児神話は、1950年代にイギリスで提唱された説が間違った形で広まったものです。三歳までの過ごし方が子どもの発達に影響を及ぼすこと自体は間違いではありませんが、従来いわれているように「母親が子育てに専念した方がよい」という説には根拠がないといえます。
また、集団保育には自宅保育にはないメリットもあります。世間一般の言説に振り回されず、それぞれのご家庭にとってのベストな形を模索することが大切です。
お子さまの英語力を育むなら、Sanrio English Masterをぜひご活用ください。Sanrio English Masterは、株式会社サンリオが提供する子ども向け英語教材です。かわいらしいキャラクターが多数登場する教材は、エンターテインメント性を重視したつくりとなっており、お子さまとおうちの方が遊びながら英語にも知育にも取り組めます。