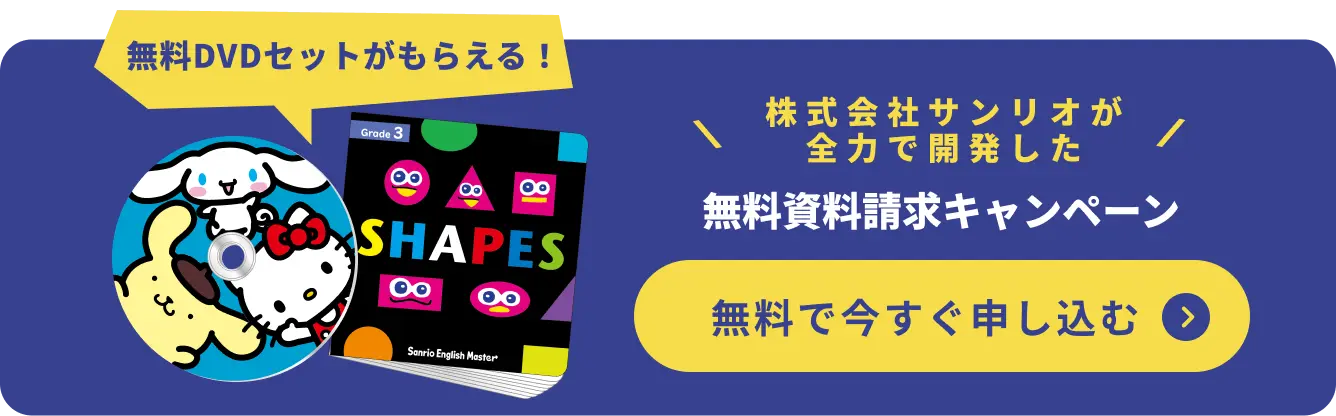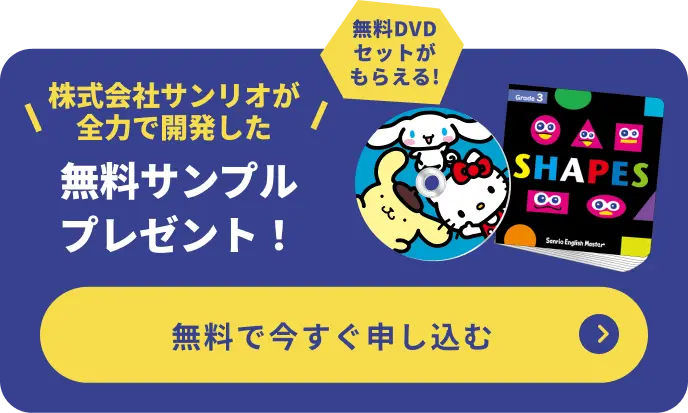なぜなぜ期とは?お子さまへの接し方のポイントや注意点などを解説

いわゆる「なぜなぜ期」のお子さまへの接し方について、どのように対応すればよいかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、なぜなぜ期のお子さまへの対応方法や、おうちの方が注意したいポイントなどを解説します。よくあるお困りごとへの対処法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
なぜなぜ期=子どもの「なぜ?」が増える時期
なぜなぜ期とは、子どもが身近にあるさまざまなものごとに疑問を持ち、質問が増える時期のことです。心理学では「質問期」と呼ばれ、周囲の大人に対して質問を繰り返すようになります。
幼児期の「第1質問期」と「第2質問期」
心理学における質問期は、第1質問期と第2質問期に分けられます。なお、第1質問期を「なぜなぜ期」と区別して「なになに期」と呼ぶこともあります。
- 第1質問期:「これなあに?」と、ものや人などの名前を知りたがる時期
- 第2質問期:「これなんで?」とものごとの原因や目的などを知りたがる時期
第1質問期の質問は、ものごとの名前についての質問なので答えが明確で、大人も答えやすいものが大半です。一方、第2質問期の質問は「どうして犬は犬っていうの?」など、ものごとの理由を知りたがるので答えにくい質問も多いでしょう。
なぜなぜ期がこないこともある?
なぜなぜ期は必ずくるものではなく、こないまま成長する子どもも少なくありません。また、なかにはなぜなぜ期といわれる年齢を過ぎてから突然、質問が増え始める子もいるでしょう。
そのため、お子さまになぜなぜ期がこなくても、とくに心配する必要はありません。もし不安な場合は、「これはどうして◯◯なんだろうね?」などの声かけをして、お子さまが疑問を持ち、自ら質問をしたくなるよう促すことも手段の1つです。
なになに期、なぜなぜ期は何歳から始まる?
なになに期となぜなぜ期は、それぞれいつごろから始まるのでしょうか?個人差があるため、あくまで目安ですが、おおむね以下のようなタイミングで始まります。
なになに期(第1質問期):2歳ごろ
なになに期とも呼ばれる第1質問期は、2歳ごろから始まるケースが多いでしょう。
目にしたものを次々「これはなに?」と聞いてきたら、なになに期が始まったサインと考えられます。
なぜなぜ期(第2質問期):3歳~4歳ごろ
なぜなぜ期とも呼ばれる第2質問期は、3歳~4歳ごろから始まるケースが多いでしょう。
ものごとの原因や目的を知りたがることが増えたり、同じ質問を何度も繰り返したりする場合は、なぜなぜ期が始まったサインと考えられます。
なぜなぜ期はなぜ訪れる?
なぜなぜ期は、子どもの自然な発達段階の1つです。では、2歳ごろから始まるなになに期を経て、どうして3歳〜4歳ごろになると「なぜ?」が増える子どもが多くなるのでしょうか?
心や社会性が発達するため
3歳~4歳ごろは、子どもの心と社会性がとくに大きく発達する時期です。保育園や幼稚園に通い始める子どもが多く、友だちとの関わりのなかで、自分が見ている世界がすべてではないことに気づいていきます。
「個」が確立するにつれ、自分以外の周りの世界にも関心を向けるようになり、ものごとに疑問を持つことが増えると考えられます。
好奇心が高まるため
3歳〜4歳ごろは、脳の発達がより一層進み、身の回りのことに対する好奇心が高まる時期です。
1日に何度も質問されると、おうちの方も疲れてしまうときがあるでしょう。しかし、お子さまの知的好奇心や学習意欲が育まれる成長過程の1つと捉えて、なるべく丁寧に向き合ってあげましょう。
なぜなぜ期を通じて身につく3つのこと
子どものなぜなぜ期は、次のような「力」や「こころ」を伸ばすために重要な時期でもあります。
1.思考力
大人から疑問に対する回答をもらえることで好奇心が満たされると、子どもの好奇心はさらにアップし、より幅広いものごとへ興味が広がります。
その結果、ものごとの違いを比べたり、仕組みを考えたり、自分で考えて答えを導き出す力が育まれるでしょう。
2.探究心や学習意欲
周りの大人が質問に答えてあげることでさまざまな知識が身につくと、「さらに深く知りたい」とものごとを探求する気持ちが育まれます。
なにかを「知りたい」という欲求は、学習意欲の向上にもつながるでしょう。
3.コミュニケーション能力
「なぜ?」という質問を通じて保護者とコミュニケーションをとることで、子どものコミュニケーション能力が発達します。
また、保護者が自分の疑問に向き合い、答えてくれるという経験を繰り返すと、家族の信頼関係がより一層深まります。おうちの方が質問に答えてくれる様子をお手本にすることで、お子さま自身が質問に回答する力も高まるでしょう。
なぜなぜ期の子どもへの接し方のポイント
なぜなぜ期のお子さまに接する際は、次の4つのポイントに気をつけることが大切です。
基本的にはその場で答える
子どもが質問をするときは、「今」答えを求めています。回答を後回しにすると興味を失ってしまうことが多いので、なるべくその場で答えてあげるようにしましょう。
子どもの好奇心が高まっているタイミングで答えてあげることが、さらなる好奇心を育むことにつながります。
子どもが理解しやすい言葉で説明する
子どもからの質問に対する保護者の答えのなかには、幼い子どもには理解することが難しいものもあるでしょう。
そういう場合は少しざっくりとした内容になってもよいので、なるべく専門用語や難しい言葉は使わず、子どもにとって分かりやすい言葉で教えてあげることが大切です。
保護者から質問をする
基本的に、質問には保護者が答えてあげる方が望ましいですが、ときおり「◯◯くん/◯◯ちゃんはどうしてだと思う?」などと逆質問をしてみることもおすすめです。
あえて答えを教えずに考えてもらうことで、お子さまの自発性や想像力が育まれます。まだ自分で本を読んで調べたり、スマートフォンで検索したりすることが難しい年齢だからこそ、「自分の頭で考える」ということができるよい機会となるでしょう。
子どもの気持ちに寄り添う
保護者にとっては当たりまえのこと、「なんでそんなことが気になるの?」と思うようなことでも、子どもにとってはワクワク、キラキラした発見であることが多いものです。
慌ただしい日々のなかでも、なるべくその気持ちに寄り添って、子どもの質問には真摯に対応してあげましょう。
【シーン別】なぜなぜ期のお困りごとへの対処法
ここからは、なぜなぜ期に「あるある」なお困りごとと、その対処法を紹介します。
ケース1.忙しくて手が離せない
子どもの質問にはなるべくその場で答えたいところですが、忙しくてどうしても手が離せないときもあるでしょう。
じっくり向き合う時間をとれないときは、「今は忙しいから、あとで一緒に調べてみようか」と提案し、時間があるときに丁寧に対応することをおすすめします。また、逆質問をして、子どもが考えているうちに用事を済ませるという手段もあります。
ケース2.質問の答えが分からない
子どもの質問のなかには、大人でも答えを知らなかったり、答え方に迷ったりするものもあります。
その場合は、インターネットや本などで、一緒に調べることを提案してみましょう。自分で調べて答えを見つけるという経験は、お子さまが成長してからも役に立ちます。
ケース3.答えがない質問をされる
ときには「どうしてあの車は赤いの?」「あの人はなんで走っているの?」など、答えを知る由もない質問をされることもあるでしょう。
そのようなときは「分からない」で終わらせるのではなく、「○○だからじゃないかな?」という答え方がおすすめです。
例えば、以下のように答えましょう。
- 「どうしてあの車は赤いの?」→「あのおうちの人は赤色が好きなのかもね」
- 「あの人はなんで走っているの?」→「今日はいい天気だし、走ったら気持ちいいからじゃないかな」
なぜなぜ期のお子さまに対するNG行動
ここからは、なぜなぜ期に避けるべき3つのNG行動を紹介します。
質問したことを否定する
質問自体を否定すると、子どもの心を傷つけてしまいます。
「◯歳なのに分からないの?」とばかにしたり、「そんなこと聞かないで」と質問自体を否定したりすることはやめるべきです。
質問に先回りして答える
幼い子どもは、自分の疑問をすんなり言葉にできず、質問に時間がかかってしまうことも多いものです。しかし、子どもが話している途中に「それは◯◯だからだよ」と、質問に先回りして答えることはやめましょう。
相手に伝えたいことを言語化するプロセスは、子どもの表現力を育むためには重要です。お子さまがうまく言葉にできずに困っているようであれば、「◯◯のことかな?」というようにやさしく誘導してあげるとよいでしょう。
質問を拒否する、無視する
子どもは、質問を通じて大人とのコミュニケーションを楽しんでいます。質問を拒否したり、無視したりすると、子どもはコミュニケーションを受け入れてもらえなかったと感じて、ショックを受けかねません。
同様に、質問を適当にかわすことも、子どもの心を傷つけてしまう可能性があります。
まとめ
なぜなぜ期は、子どもの知的好奇心や学習意欲を育む大切な時期です。また、質問と回答のプロセスを繰り返すことは、思考力やコミュニケーション能力の向上にもつながります。忙しいときでもなるべく真摯に対応し、お子さまの好奇心を満たしてあげましょう。
お子さまの英語力を育むなら、Sanrio English Masterをぜひご活用ください。Sanrio English Masterは、株式会社サンリオが提供する子ども向け英語教材です。かわいらしいキャラクターが多数登場する教材は、エンターテインメント性を重視したつくりとなっており、お子さまとおうちの方が遊びながら英語学習にも知育にも取り組めます。