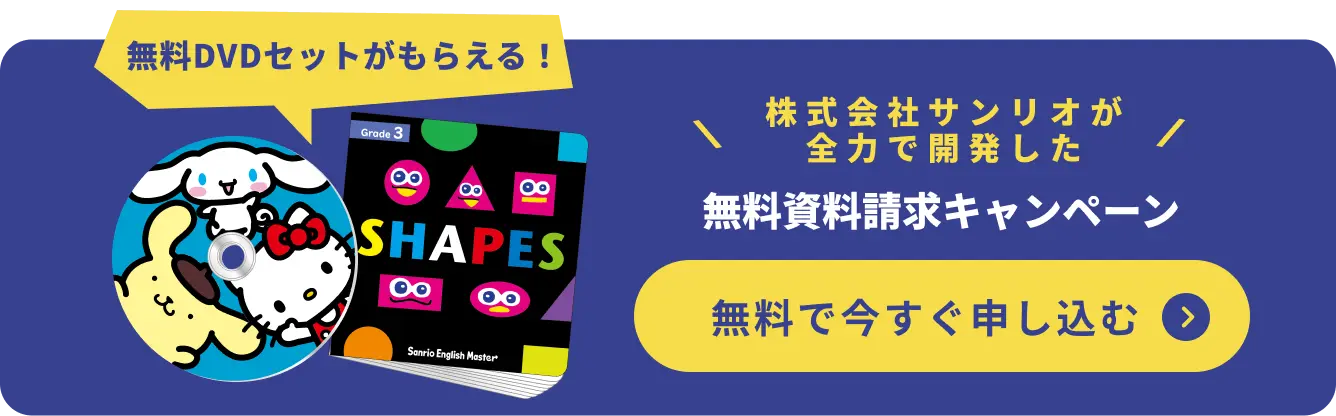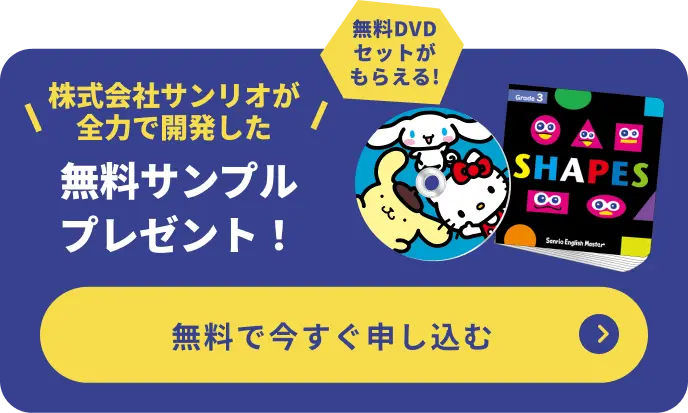粘土遊びのねらいとは?粘土の種類や特徴を知り創造力や発想力を磨こう!

子どもの粘土遊びにはさまざまなメリットがあり、子どもの成長を促すことができます。日常に粘土遊びを取り入れれば、成長が実感できるでしょう。
この記事では、子どもの粘土遊びのねらいや粘土の種類と特徴、粘土遊びがしやすくなる方法などを紹介します。粘土遊びのルールも解説するので参考にしてください。※本記事は、幼児や小学生が対象です。
目次
粘土遊びのねらい
子どもに粘土遊びをさせるねらいを知っておくと、効果を得やすくなります。ここでは、4つのねらいを紹介します。
子どもの手先が器用になる
子どもに粘土遊びをさせるねらいの代表的なものが、手先が器用になることです。粘土遊びでは、こねる、丸めるなど手先を使った動作を繰り返すため、夢中になればなるほど手先の動かし方が身につきます。さらに、道具を使えば、手先の器用さだけでなく脳の発達も促されます。
子どもの想像力が豊かになる
粘土遊びにより、子どもの想像力が豊かになることもねらいの1つです。子どもが粘土遊びをすれば、自由に発想しさまざまな形を作ることでしょう。その繰り返しが想像力を豊かに育てます。同時に、豊かな発想力も身につきやすくなります。
子どもが粘土遊びに慣れてくれば、完成をイメージしながら粘土に触れるようになるでしょう。完成をイメージし、粘土遊びをすることは、子どもの想像力を豊かにするうえで大事なポイントです。粘土にボタンや木の葉などほかのアイテムを組み合わせれば、発想力がさらに豊かになります。
子どもの集中力が高まる
子どもは、粘土遊びが楽しければ楽しいほど、集中力を持続させて遊びに没頭するものです。粘土遊びには、子どもの集中力を高める効果も期待できます。
粘土遊びが楽しくて、夢中になれる仕掛けを工夫すれば、子どもは集中して粘土遊びをするでしょう。結果として、子どもの集中力を高める効果にもつながります。これを繰り返すことによって、さらに集中力を高められます。
子どもの五感が磨かれる
子どもが粘土遊びに集中すれば、五感を磨く効果が期待できるでしょう。子どもが粘土に触ることで、粘土の感触や温度などを肌で感じます。これは、子どもの触覚を磨くことにつながります。また、粘土に触れることで発する独特の音を聞き取ることで、粘土の状態などが分かるようになり聴覚も磨かれるでしょう。
色を混ぜ合わせることで、色彩感覚も磨かれるでしょう。
粘土の種類と特徴
粘土遊びには一般的に小麦粘土が多く使用されていますが、ほかの種類もあります。ここでは、粘土の種類と特徴を解説します。
小麦粘土
小麦粘土は、小麦粉と水が主原料の粘土です。食材を利用しているため、小さな子どもにも適しています。柔らかく、変形や成形がしやすいことが特徴です。また、自宅で手作りすることもできるため、粘土を作るところから、子どもと遊べることもポイントになります。注意点は、小麦アレルギーの子どもに使用しないことです。小麦アレルギーがある場合は、米粉粘土などを使うようにしましょう。
紙粘土
紙粘土は、パルプや水、炭酸カルシウム、糊剤などを混ぜ合わせた粘土です。市販されていますが、手作りすることも難しくはありません。軽くて扱いやすく、成形もしやすい粘土で、乾燥すれば固まることが特徴です。他の粘土に比べて固まりやすいため、作品として保存するような場合に適しています。
油粘土
油粘土は、鉱物粉に植物性の油や鉱物性の油などを混ぜて作られた粘土です。油が含まれているため乾燥しにくいことが特徴で、子どもが何度でも粘土遊びを楽しめます。ただし、固まりにくいので、作品として残すのには不向きです。
土粘土
土粘土は、天然の土壌から採掘した粘土素材に砂を混ぜて作った粘土です。土や砂の匂いがして自然を感じられる粘土であり、子どもに天然素材を感じさせたい場合に適しています。特徴は、乾燥しやすいことです。乾燥すると固くなりますが、水を加えると柔らかくなります。焼くと固くなるため、作品として長く残したいときにおすすめです。
寒天粘土
寒天粘土は寒天の粉末と水を練り合わせて作られた粘土です。これまでに紹介した粘土と異なり、ゼリーのような感触で、形を変えるのは簡単ですが、作品として残すのは難しいでしょう。ただし、安全な素材であるため、小さな子ども向けの感触遊びとして取り入れやすい粘土です。
粘土遊びがしやすくなる方法
粘土遊びで子どもを飽きさせないためには、いくつかの方法があります。ここでは、代表的な方法を3つ紹介します。
絵本や図鑑を利用する
子どもが粘土遊びに夢中になるためには、ある程度のモチーフが必要です。例えば、粘土遊びに適した絵本を読み聞かせたり、作品のテーマとなるような図鑑を見せたりすれば効果が期待できるでしょう。
実際に作るものを見せる
テーマが決まっている場合は、実際に作るものを見せることが効果的です。実物を見せると、実物に近づけようとする創造力や発想力、実行力などが働きやすくなるでしょう。大人が見本となる作品を準備したり、美術館などに連れて行ったりすることも効果的です。
事前準備としてお絵かきする
粘土遊びの事前準備として、お絵かきをしておくことは有効な手段です。お絵かきをすることで、粘土で作り上げる作品のイメージが固まりやすくなります。紙粘土であれば、紙粘土の作品に色付けする前に先に塗り絵をしておけば、予行練習になるでしょう。お絵かきで描いた絵を立体化することは、子どもの想像力や発想力を刺激します。
子どもに教える粘土遊びのルール
粘土遊びを始める前に、子どもに教えておくルールがあります。ここでは、そのルールについて紹介します。
粘土板の上で遊ぶ
子どもが粘土遊びをする際には、粘土板の上で遊ぶことをルールとして教えましょう。粘土で周りを汚したり、作品にゴミが混入したりすることを防げます。粘土板がなかったり、広い範囲で遊ばせたりしたい場合は、机にビニールクロスなどを敷く方法も有効です。
粘土を口に入れない
小さい子どもはなんでも口に入れて、舌で感触や形を確認します。粘土も口に入れてしまうおそれがあるため、小麦粘土や米粉粘土のような食材でできている粘土であっても、口には入れないように注意しましょう。
粘土を投げない
子どもは、物を投げて遊ぶことがあります。粘土を投げて遊ぶケースも少なくはないでしょう。粘土に限らず物を投げることは、してはいけないと言い聞かせたり注意したりすることが大事です。また、粘土を落とす可能性が高ければ、ブルーシートなどを敷いて対策をしておくと、掃除がしやすくなります。
粘土遊びで配慮するポイント
子どもの粘土遊びには、配慮しなければならないポイントがあります。ここでは、そのポイントを3つ紹介します。
子どもを見守る
子どもが粘土遊びをしている際には、大人が見守るようにしましょう。先に述べたように、子どもは粘土を口に入れたり、投げたりする可能性があります。他にも、思いもよらない行動をする可能性は否定できません。小麦粘土で突然アレルギー反応が出るケースもあるため、油断せずに子どもを見守ることが大事です。
事前に環境を整える
子どもが夢中になって粘土遊びができる環境を、事前に整えることも大事です。床にブルーシートを敷いたり、机が汚れないように粘土板が滑りにくいビニールクロスを準備したりしましょう。種類にもよりますが、粘土の汚れは落ちにくいため、汚れてもよい服装にすることがおすすめです。
創造や表現を尊重する
粘土遊びに夢中になっている際は、子どもの創造や表現を大切にしましょう。粘土遊びのねらいを阻害しないように心がけると、子どもの成長を間近で感じられるかもしれません。大人が作品を否定したり、手直ししたりすることは、子どもの成長を止めることになります。お子さまから質問された場合は的確にアドバイスしてあげましょう。
まとめ
子どもの粘度遊びは、子どもの創造力や指先の発達を促し、集中力や想像力を養う効果が期待できます。お子さまの学びや成長のために、ぜひ取り入れてみてください。
Sanrio English Masterなら、0歳から8歳まで学べる充実したカリキュラムで、英語だけではなく「考える力」「運動する力」「調べる力」が育ちます。お子さまが遊びを通して学べる教材です。
Sanrio English Masterにはサンリオの新キャラクター「ピタ」が登場します。このキャラクターは身体を粘土のようにさまざまな形に変え、相棒のエディとともにお子さまの学習をサポートします。
また、Sanrio English Masterにはアルファベット積み木があるため、積み上げたり、好きな単語を作ったりなど創意工夫ができることが特徴の1つです。そのため、お子さまの創造力を養うことが期待できます。ぜひ無料サンプルでお試しください。