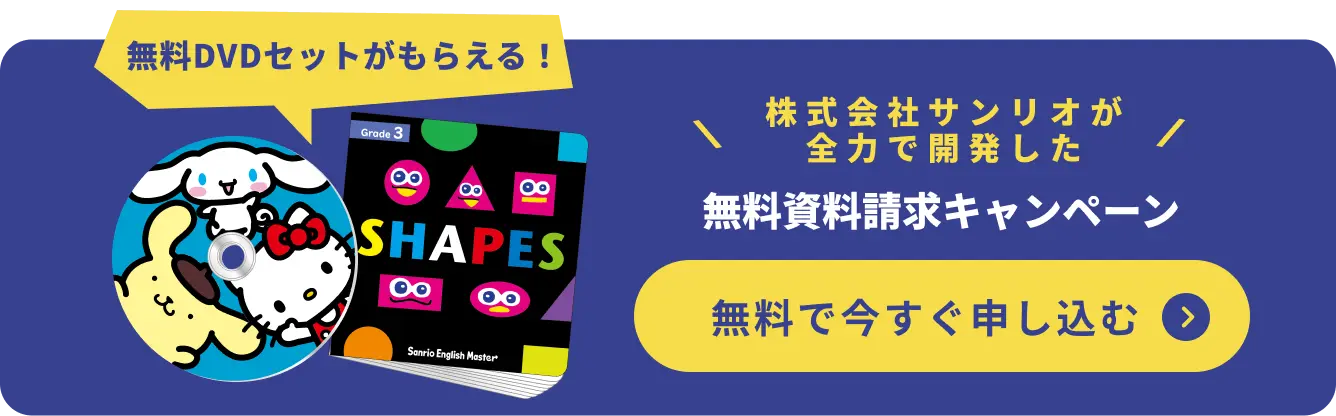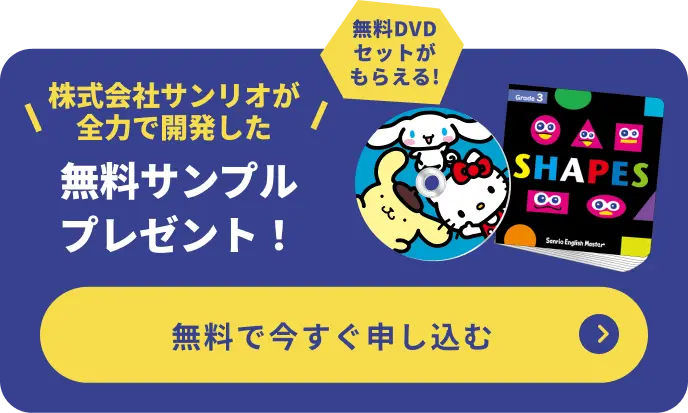子どもの言語発達の過程を年齢別に解説|話し始めない理由も紹介

お子さまの言語発達に関心があり、どのように子育てを行えばよいか悩んでいるおうちの方もいるでしょう。
当記事では、子どもの言語発達の過程や話し始めない理由などについて解説します。お子さまの言語発達に興味があるおうちの方は参考にしてください。
目次
発語とは
赤ちゃんにおける発語とは、赤ちゃんがなんらかの形で言葉を発する行為を指します。最初は「あー」や「うー」から始まり、成長とともに単語や簡単なフレーズを使ってコミュニケーションを取るようになります。
赤ちゃんの発語を促すためには、日常的におうちの方が積極的に話しかけることが大切です。
子どもの言語発達過程
ここでは、子どもの言語発達過程について解説します。
1歳まで
赤ちゃんの言語発達は、音を発することから始まります。この時期に見られる特徴的な発語が「喃語(なんご)」です。喃語とは「ばばば」や「だだだ」といった子音と母音が続く言葉を指します。まだ意味を持った言葉ではない点を押さえておきましょう。
1歳~1歳半
1歳から1歳半にかけて、子どもは「一語文」を話し始めます。一語文とは「わんわん」や「まんま」のように意味のある単語を単独で使う言葉です。
この時期は、言葉と身振りを組み合わせて、自分の意思を表現しようとする姿が見られるようになります。例えば「わんわん」と言って犬を指すなどです。
1歳半~2歳
1歳半から2歳の時期、子どもは「二語文」を使い始めます。二語文とは、2つの単語を組み合わせた簡単な文章を指し、「ママ いく」や「ボール ちょうだい」のような表現です。
この時期には、名詞と名詞、または名詞と動詞を組み合わせることで、表現の幅が大きく広がります。二語文によって、子どもはより具体的なコミュニケーションを取れるようになります。
2歳~3歳
2歳から3歳にかけて、子どもの言語能力はさらに発達し「三語文」を使えるようになります。三語文とは、3つの単語を組み合わせた文章のことです。この時期になると、子どもは大人の話し方や表現を真似し始めるため、使う言葉の幅がさらに広がっていきます。
また、簡単な形容詞を使えるようになる点も特徴です。さらに「どっちがいい?」や「どっちに行きたい?」といった二択の質問に対して、自分の意思を言葉で伝えられる時期でもあります。
3歳~4歳
3歳から4歳になると、子どもは「複文」を使えるようになります。複文とは、主節と従属節から成る文のことです。これにより、子どもはその日に起こった出来事や自分の気持ちをより詳しく説明できます。
また、この時期には助詞も使えるようになります。
4歳~5歳
4歳から5歳の時期には、代名詞を使えるようになります。また、この年齢では同じ年代の子どもたちとコミュニケーションを取る機会が増え、会話を楽しむ姿が見られるようになります。
さらに「かっこいいから、これがいい」といったように、自分の意見の根拠を示して伝える能力も発達する点が特徴です。
5歳~6歳
5歳から6歳になると、子どもは自分の体験を自分の言葉で伝えられるようになり、簡単なスピーチも可能になります。
5歳の子どもが持つ語彙数は約2,000~2,500語といわれています。この時期は、子どもが言葉を積極的に使いたいと感じるようになるため、楽しく話せる環境を整えることが大切です。
子どもがなかなか話し始めない理由
ここでは、子どもがなかなか話し始めない理由について解説します。
言葉の習得が遅れている
子どもが話し始めるのが遅い理由として、言葉の習得がほかの子どもに比べて遅れている場合があります。このようなケースでは、発語が遅れることもあります。
しかし、言葉の発達には個人差がある点を覚えておきましょう。一時的に遅れているように見えても、ある時期から急速に追いつくことも珍しくありません。
言葉に触れる機会が少ない
日常的に言葉に触れる機会が少ない場合、言葉の習得が遅くなる可能性があります。例えば、家庭内でお子さまが話さなくても、おうちの方が子どもの意図を察してサポートする環境では、子どもは話す必要性を感じにくくなるでしょう。
また、自然に耳に入ってくる会話や人とのコミュニケーションが少ない場合も、習得が遅くなりがちです。言葉に触れる機会が多いほど、子どもはしゃべり始めやすくなる点を押さえておきましょう。
おとなしい性格
おとなしい性格の子どもは、元々積極的に話すことが少ない場合があります。しかし、呼びかけに反応し、大人が話しかける内容を理解している様子が見られれば、大きな問題ではありません。このような場合は、無理に話すことを促さず、子どものペースに合わせたコミュニケーションを取りましょう。
障害を抱えている可能性も考えられる
あまりに言葉をしゃべり始めるのが遅い場合は、子どもが障害を抱えている可能性も考えられます。考えられる障害は、以下の通りです。
- 聴覚障害:難聴などの障害によって、耳が聞こえていないために言語の習得が遅れている可能性がある
- 発達性言語障害:発語のみが遅れる表出性言語障害、あるいは言葉への理解と発語が遅れる受容性言語障害の可能性がある
- 発達障害:ASDなどを抱えており、人とのコミュニケーションを取るための発達が遅れている可能性がある
など
なかなか話し始めない場合におうちの方ができること
ここでは、お子さまがなかなか話し始めない場合に、おうちの方ができることについて解説します。
積極的に話しかける
子どもは、周囲の大人が話す言葉を聞きながら自然に言葉を覚えていきます。そのため、日常生活のなかで積極的に子どもに話しかけることが大切です。
また、子どもの周りで起きている出来事と言葉が結びつくように工夫することも効果的です。例えば、散歩中に「わんわんが歩いているね」と犬を指差しながら話してあげるとよいでしょう。
動作を実況する
子どもの動作や行動を実況するように話しかけることも、言葉の習得を助けます。例えば「おもちゃを箱に入れたね」といった、具体的な表現にしてあげることで、子どもは自分の行動を認識しやすくなります。
また、子どもが何かに興味を示しているときは、その瞬間を逃さずに積極的に声をかけてあげましょう。
優しくゆっくり話す
子どもが言葉に集中しやすいのは、周囲の大人が優しくゆっくり話しかけたときだといわれています。早口で話されると、子どもが内容を理解しづらくなり、言葉への関心が薄れる場合もあります。
そのため、子どもがリラックスして言葉に耳を傾けられるように、穏やかなトーンで、ゆっくりとしたペースで話すことを心がけましょう。
相づちを打つ
子どもは「自分の話を聞いてもらえている」と感じると、話す意欲が高まります。そのため、子どもの発言や動作に対して積極的に相づちを打ち、聞いている姿勢を示すことが大切です。
また、子どもと同じものを見て「これ、赤いね」と共有することも効果的です。
言語発達に活用できるもの
ここでは、お子さまの言語発達に活用できるものを解説します。
絵本
絵本の読み聞かせは、子どもが言葉を覚えるうえで効果的な手法です。また物語を通して社会性やコミュニケーション能力を育むことができ、子どもが他者と関わる力の基礎を築けます。
さらに、物語の登場人物の気持ちに触れることで、感情への理解も深まります。
歌
歌を用いることで、子どもは楽しく言葉を学べます。特に、わらべ歌は発語を促すのに適しており、リズムに合わせて簡単な歌を繰り返し歌うことで、言葉への興味を引き出せるでしょう。
わらべ歌には、遊びの要素も含まれており、子どもが自然と楽しい気持ちで言葉に触れるきっかけになります。
言語発達が遅れていても見守ることが大切
子どもの言語発達が思うようには進まない場合でも、焦らずに温かく見守る姿勢が重要です。子どもはそれぞれ異なるペースで成長するため、言葉を話し始める時期にも個人差があります。
子どもが話した言葉に間違いがあったとしても、何度も指摘を繰り返すと、子どもが言葉を使うこと自体を嫌いになってしまう可能性があります。間違いに気づいても優しく受け止め、子どもにペースを合わせながら言語発達を促していくとよいでしょう。
発育の相談ができる場所
言語発達が遅れている場合には、専門家に相談をしてみてもよいでしょう。発育の相談ができる場所は、以下の通りです。
- 子育て支援センター:子育てに関わる悩みを相談できる場所であり、発育や発達に関するアドバイスを受けられる
- 保健センター:発達や発育に関することを相談可能で、保健指導や健康調査、健康教育などのサポートも受けられる
など
まとめ
どのタイミングで発語をするかは、子どもの発達状況や個性によって異なります。子どもとコミュニケーションを取りながら、自然な形で発達が進んでいくようにサポートしましょう。日本語の習得が進んできたら、徐々に英語学習を進めていく取り組みもおすすめです。
Sanrio English Masterなら、お子さまとおうちの方がともに遊びながら英語表現を覚えられます。お子さまの英語教育に関心があるおうちの方は、まず無料サンプルをお試しください。