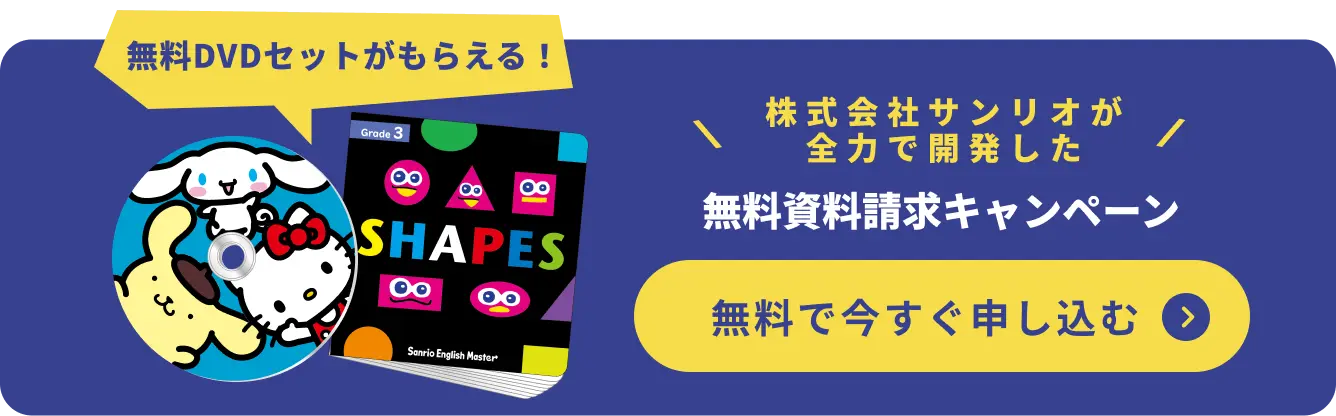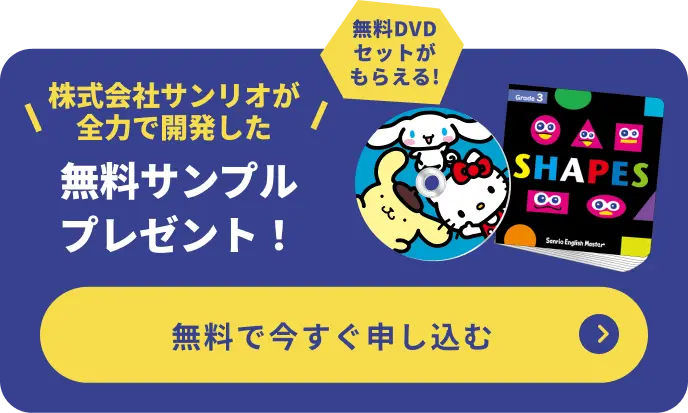2歳児のお昼寝は何時間が最適?必要な理由や寝ない際の対処法などを解説

2歳頃は主張が増え、すんなりお昼寝しないことも珍しくありません。そのため、両親としてはお昼寝のことで悩みやすい時期だといえます。
この記事では、お昼寝が重要である理由やお昼寝の時間の目安などを解説しています。2歳のお子さまがいて、お昼寝の時間で悩んでいる方は参考にしてください。
目次
2歳児には基本的にお昼寝が必要
結論としては、2歳児にはお昼寝が必要です。2歳になると話せる言葉が増え、運動能力も高まります。ただし、まだまだ大人のような体力や集中力はありません。お昼寝で適度に身体を休ませて心身のリフレッシュをしないと、疲れたり眠くなったりして、機嫌を損ねやすくなる原因となります。
お昼寝が重要である理由
お昼寝は、子どもの生活のリズムを構成する重要な要素です。厚生労働省の「保育所保育指針」にも記されています。ただし、すべての子どもが同じようにお昼寝を必要とするわけではありません。発達状況に合わせた調整が望ましいとされています。以下で、お昼寝が重要である3つの理由を解説します。
心身が健康に保たれるため
お昼寝は、心身を健康に保つ効果があります。子どもは眠気によって疲れが溜まり体調不良に陥ると、注意力や集中力などが低下し、転倒のような事故でケガをすることも考えられます。
眠気と自律神経のバランスは関係しており、眠くなるとイライラしたり、小さな出来事で不安な気持ちになったりすることもあるでしょう。お昼寝によってリスクを軽減し、午後から再び活発な活動が可能になります。
記憶力がアップするため
お昼寝によって、記憶力アップが期待できます。アメリカ・マサチューセッツ大学の研究によると、3~6歳の幼児40人に実施した記憶力テストで、お昼寝をしたケースはしなかったケースと比べてスコアが10%アップしました。
この効果は翌朝にも見られ、お昼寝は「脳の記憶領域を整理し、記憶力向上に効果がある」という結果となっています。そのため、お昼寝によって記憶力が向上し、学力のアップも期待できるでしょう。
参考:Naps Nurture Growing Brains
免疫力の向上が期待できるため
2009年に発表された研究結果によると、お昼寝によって免疫力の向上が期待できます。睡眠時間が7時間未満の人は、8時間以上の人と比べて3倍近く風邪を引きやすいという結果になりました。睡眠中は「メラトニン」というホルモンが分泌されます。メラトニンは、免疫力を向上させたり身体の成長を促したりする効果があります。
2歳児に適したお昼寝の時間
お昼寝の時間帯や長さによっては、夜の睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。2歳児は1日に1~2時間のお昼寝を目安にしましょう。昼食後の、12時30分~14時30分頃が一般的な時間帯です。ただし、まったくお昼寝しない子どももいます。また、2時間以上のお昼寝や15時以降からのお昼寝は、夜更かしにつながりやすいため極力避けましょう。
睡眠不足が与える影響
2歳児は、1日に約11~13時間もの睡眠が必要とされています。そのため、夜の睡眠時間が10時間であれば、1~2時間のお昼寝で補うことが必要だという計算になります。お昼寝をしない子どももいるため、日中に問題なく活動できていれば様子を見ましょう。
ただし、子どもが睡眠不足になると、肥満やうつ病になりやすくなります。部屋の環境や生活リズムを整えても何日もまとまった時間眠れなかったり、日中ボーっとしたりする場合は、専門家への相談を検討しましょう。
子どもがお昼寝しやすくなる方法
毎日のお昼寝の時間を決めていても、日によってうまく眠れなくなる子どもも珍しくありません。そのため、どうすれば寝てくれるのか悩むおうちの方も多くみられます。お昼寝しやすくなる、4つの方法を解説します。
部屋の環境を整える
お昼寝を促し、質の高い睡眠をとらせるためには、部屋の環境が重要です。カーテンを閉めたり照明を消したりして、部屋を暗くしましょう。部屋が明るいと寝付けない子どももいるためです。また、エアコンを使用して温度や湿度を快適に整えることも重要です。
添い寝する
2歳児の場合、まだまだ添い寝してもらわなければ眠れない子どもも珍しくありません。人の温もりを感じられることで、子どもは安心できます。不安な気持ちをなくすために、一緒に横になり添い寝をしましょう。
お昼寝前は身体を動かす
睡眠は体力を回復する役割もあり、体力が余っていると眠りにくくなります。一方でお昼寝前に身体を動かし、体力を消耗していると寝やすくなります。お昼寝の時間が短かったり眠れなかったりする場合は、午前中から昼食までの時間帯に、身体を動かす遊びを増やすよう意識しましょう。
入眠への流れを作る
寝る前に毎回実施する、入眠への流れを作りましょう。たとえば、絵本を読み聞かせたり、静かな音楽をかけたりするなどがおすすめです。子守唄やオルゴールなどの曲も有効です。2歳児の場合、子どもと相談して流れを決めておき、あらかじめ決めた内容を守って、せがまれても引き延ばさないことが大切です。
生活や睡眠のリズムを整えるための習慣
子どもによってお昼寝の長さや眠りやすさは異なり、なかなか眠らない子どもも珍しくありません。遊びに夢中になり、お昼寝を嫌がることもあるでしょう。生活や睡眠のリズムを整えるための、3つの習慣を解説します。また、どうしても眠らない場合は、親子のストレスにならないことを意識しましょう。
早寝早起きをする
生活リズムを整えることは重要です。2歳児であれば、朝は6~8時までには起き、夜は7~8時に寝ることが理想です。遅くとも、夜9時までには寝かせましょう。寝る時間が遅いと寝不足になりやすく、それに合わせて起きる時間が遅くなると生活リズムが崩れやすくなります。早寝早起きをしたうえで、お昼寝によって必要な睡眠時間を補うようにしましょう。
朝食をしっかり食べる
朝食はしっかり食べるようにしましょう。小さな子どもは1度あたりの食事量が少ないため、朝食を摂らないと栄養素が不足する原因となりやすいためです。
加えて、朝食を食べると体温が上がって身体や脳が活性化し、活動するための準備ができます。また、消化器の働きを活発にし、排便を促す意味もあります。早寝早起きの生活リズムと同様に、朝食は大切な習慣です。
日光をたっぷり浴びる
人間の睡眠と覚醒のサイクルは24時間よりも長く、朝日を浴びることで体内時計のリセットにつながります。特に午前中に日光を浴びることで、早寝早起きの生活リズムを作りやすくなるでしょう。
また、日光を浴びると、脳を覚醒させる効果のある「セロトニン」が分泌されます。午後にお昼寝し、さらに夜も十分に眠れるよう、午前中を中心に日光をたっぷり浴びるよう意識しましょう。
無理に寝かせない
生活リズムやその日の体調によっては、お昼寝しないこともあります。うまく眠れない日も珍しくないため、無理に寝かせようとしないことも重要です。目を閉じて横になるだけでも、ある程度身体を休めることにつながります。周囲に絶対に合わせようとするのではなく、その日の状況やその子に合った対応が大切です。
まとめ
2歳児には基本的に1~2時間のお昼寝が必要です。部屋の環境を整えたり、添い寝したりして寝やすくなるよう意識しましょう。ただし、うまく寝付けない日も珍しくないため、その場合は親子がストレスを溜めないことが重要です。
お子さまの自立心や集中力を向上させたいと考えている場合、Sanrio English Masterをぜひご活用ください。株式会社サンリオが提供する子ども向け英語教材で、可愛らしいキャラクターが多く登場します。お子さまが楽しく学べる設計で、遊びながら自然と英語や知育に取り組めます。