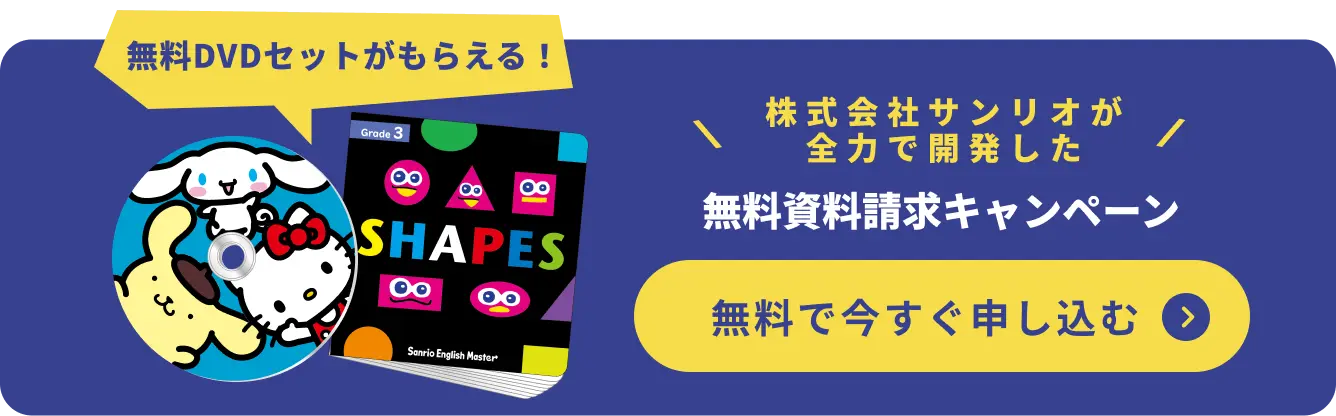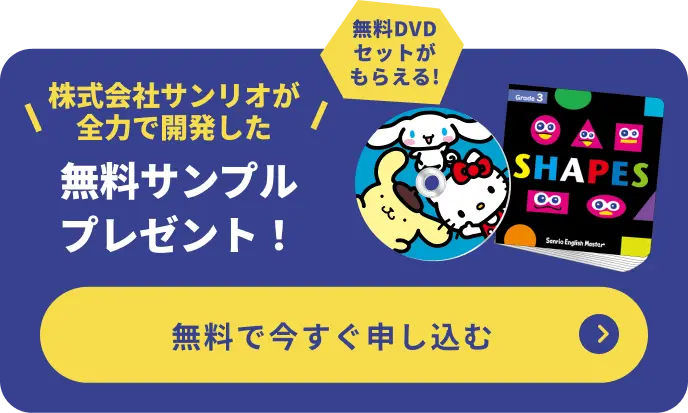3歳児の癇癪はどうすればいい?癇癪を起こす理由や対処法を紹介!

3歳児は、一般的に癇癪を起こしやすい時期とされています。何を言っても泣いたり怒ったりすることがあるため、対応に困っているおうちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では3歳児が癇癪を起こす理由や、対処方法などを解説します。癇癪を起こしているときに避けるべき行動や、わがままとの違いの見極め方も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
3歳児は癇癪を起こしやすい時期
3歳頃に起きる癇癪は、第一次反抗期であり、イヤイヤ期とも呼ばれています。少しのことで泣いたり怒ったりして、感情を爆発させるのが特徴です。
イヤイヤ期は成長過程の一部であり、自我が発達している証拠です。言葉での感情表現が未熟であるが故に、癇癪という形で気持ちを表現してしまいます。
3歳児が癇癪を起こす理由
3歳児はなぜ癇癪を起こしやすいのでしょうか。その理由を解説します。
3歳児は自我が芽生える頃
3歳児は自我が芽生え始める時期であり、何でも自分でやってみたいと考える傾向にあります。それにより保護者に反抗して、自己主張が激しくなります。
しかし、何かをしようと思っても、体が未発達なため、物事を思い通りに進められないことがあります。また「理性」や「我慢」を担う脳の機能が未熟で、感情をうまく表現できず、癇癪という形で表現されます。
日常で癇癪を引き起こすきっかけ
日常生活で癇癪を引き起こすきっかけはいくつもあります。主なきっかけとして、以下のようなものが挙げられます。
- 生活リズムの狂い(食事の時間、寝る時間、起きる時間など)
- 疲労や空腹
- 過剰な刺激(大きな音、明るい光、人がたくさんいるにぎやかな場所など)
- 身支度・トイレ・食事・靴を履くなど、自分でしたかった行為を大人が手伝ったとき
また、「これが欲しい」「これが嫌だ」「これがしたいのにできない」など、保護者や環境など何かしらの理由で自分の思い通りにいかない状況は、子どもにとってストレスです。ストレスを感じると癇癪を起こしやすい傾向にあります。
3歳児の癇癪に見られる行動
個人差はありますが、3歳児が癇癪を起こすと、さまざまな行動をしがちです。ここでは、一般的なものを2つ紹介します。
周囲に手が出てしまう
3歳頃の子どもは言語能力が未発達であり、自分の気持ちを言葉で表すことがなかなか難しいです。そのため、癇癪を起こした際は、言葉よりも先に行動で感情を表現してしまいがちです。
抑えきれない思いを伝える手段として、叩く・つねる・押す・蹴るなどの行動を取るようになります。
物を投げてしまう
おもちゃや身の回りにある物を投げてしまうのも、3歳児の癇癪で起こりやすい行動のひとつです。柔らかい物であれば投げられてもほとんど問題ありませんが、固い物だと周りの方にとってケガの危険があるため注意が必要です。
子どもに物を投げないように伝えても、気分や状況によっては、さらに状況が悪化する場合もあります。
3歳児の癇癪への対処法
3歳児が癇癪を起こしたときは、どのように対応するとよいのでしょうか。具体的な対策を紹介します。
気持ちを受け止める
お子さまが癇癪を起こした際は、まず気持ちを受け止めることが大切です。行動ばかりに目を向けて注意するのではなく、行動の裏にあるお子さまの気持ちを汲めるように向き合いましょう。
お子さまの気持ちを代弁してあげると、お子さまは「自分の気持ちを理解してくれた」と感じ、安心感を得られるため、落ち着きやすくなります。
理由を説明する・代案を提案する
お子さまのしたい行動が、「なぜできないのか」という理由を説明しましょう。より思い通りに行動できる方法があれば、代案を提案してあげるのがおすすめです。
すぐに代案を提案するのではなく、お子さまの気持ちを一旦受け止めてから、別の案を提案すると受け入れてもらいやすくなります。
癇癪を起こしにくい環境の整え方
3歳児が癇癪を起こしにくい環境を整えてあげることも大切です。意識した方がよいポイントを解説します。
やりたいことを禁止されにくい環境にする
やりたいことができないと、ストレスを感じて癇癪を起こす子どもは多い傾向です。やりたいことを禁止されにくい環境を整えてあげると、ストレスを感じる頻度を低減させられます。
具体的には、子どもの周りに触ってはいけない物や、投げてはいけない物を置かないようにするのが効果的です。子どもにとって危険な物を手に取っている姿を見ると、どうしても静止したり注意したりするため、保護者のストレスにもつながります。
子どもが興味を持っても大丈夫な物だけを周りに置くことで、お子さまにストレスを与えにくい環境を作れるでしょう。
心に余裕を持つ
保護者のコンディションも、子どもにとっては重要な環境のひとつです。おうちの方の心に余裕がないことは、お子さまにも伝わってしまう上に、お子さまの行動を落ち着いて受け止めにくくなります。
周囲に協力を仰げるならば、積極的にサポートをしてもらい、育児の負担を軽減することも大切です。おうちの方の心がリフレッシュできれば、お子さまに優しい気持ちで接することができ、癇癪が起きにくくなるでしょう。
3歳児の癇癪対応で避けるべき行動
3歳児が癇癪を起こしたときの対応として、3つの避けるべき行動を紹介します。
約束を破る・言っていることを変える
おうちの方が約束を破ったり、言っていることを変えたりしないように心がけてください。おうちの方が約束を破ってしまうと、お子さまが約束を軽んじるようになってしまう可能性があります。一度決めたことは厳守するように意識しましょう。
また言動に一貫性がないと、お子さまからの信頼が損なわれる原因にもなりかねません。
お子さまの話を聞かない
お子さまの話を聞かないような態度は、避けるべきです。おうちの方にとって、お子さまの主張は理不尽に感じられる場合もあるでしょう。しかし、お子さまにとっては合理的な理由がある可能性があります。
まずはお子さまの話を聞き、主張の裏にはどのような思いがあるのか理解することが大切です。
頭ごなしに叱る・脅す
頭ごなしに叱ったり、脅したりするのは避けましょう。頭ごなしに叱るだけでは、お子さまが萎縮する原因になります。お子さまと保護者の信頼関係に亀裂が入り、状況の悪化につながりかねません。
また、脅して言うことを聞かせるという行為も、お子さまを怖がらせるだけです。一時的に言うことを聞いてくれたとしても、根本的な解決になりません。
3歳児の癇癪とわがままの見極め方
3歳児の「癇癪」と「わがまま」には違いがあります。子どもによって差はありますが、癇癪とわがままには以下のような違いがあります。
- 癇癪:欲求不満などが原因で感情を抑えられず、周囲に手が出てしまったり、物を投げてしまったりする
- わがまま:他人や周囲の都合や事情に関係なく、自分勝手な行動や発言で自分の欲求を通す
癇癪とわがままの違いの見極め方について、以下で詳しく解説します。
わがままには種類がある
お子さまのわがままを「理不尽な要求」と決めつけて叱ってしまうと、感情の抑制につながってしまいます。しかし、理不尽な要求をむやみに容認することも、教育上よくありません。
子どものわがままには、理不尽な要求である「注意すべきわがまま」と、成長の過程で欠かせない自己主張や意見である「OKなわがまま」があります。わがままの種類を見極めて対応するよう心がけましょう。
わがままの判断基準
わがままの種類を判断する基準として、「周囲に迷惑をかけないか」を確認しましょう。周囲に迷惑をかけないと判断されたわがままであれば、容認しても問題ありません。
例えば、晴れの日にお子さまが「長靴を履きたい」といって癇癪を起こした場合、おうちの方から見て「雨が降っていない」「歩きにくい」など、疑問に思うことがあるでしょう。おうちの方が違和感を覚えても、お子さまは長靴を気に入って履いているという可能性があります。
また、おうちの方が先回りして失敗を防止しようと行動を制限してしまうと、過干渉につながり、お子さまの経験を奪ってしまいます。
3歳児の癇癪はいつ落ち着く?
お子さまの癇癪は、感情を言葉で表現できるようになると、次第に落ち着いていきます。「イヤ」という言葉以外にも、「悲しい」「怒っている」など具体的な言葉が使えるようになると、感情のコントロールが上達していると判断できます。
癇癪が落ち着く時期の目安として、4歳頃になると癇癪が治まることが多いといわれています。
子どもの癇癪・発達障害の違い
癇癪と発達障害の違いを理解し、お子さまの成長しやすい環境を整えましょう。
発達障害の判断方法
発達障害とは、脳機能の発達が関係する障害で、癇癪とは異なります。癇癪と発達障害の特性は似ている点もあるため、「もしかしたら発達障害かも」と感じるかもしれませんが、一概にそうであるとはいえません。
お子さまが発達障害かどうかを判断する基準は、主に以下の通りです。
- 話が一方的でやりとりしにくい
- ひとつのことに集中すると話しかけても気づかない
- ささいなことでも注意されるとカッとなりやすい
- 思い通りにならないとパニックになる
上記の判断基準はあくまで一例であるため、最終的には医師の診断が必要となります。お子さまの状態が気になる場合、まずは専門機関に相談するとよいでしょう。
子どもの発達障害の相談先
お子さまが「発達障害かもしれない」と感じた場合は、自治体の発達障害者支援センターなどの専門機関に相談してみてください。おうちの方がお子さまに対して感じていることや、幼稚園や保育園の先生から聞いた普段のお子さまの様子をまとめておくと、相談がスムーズに進みやすいです。
お子さまとの時間を設けるならSanrio English Master
お子さまと自宅で楽しく遊びながら英語も学ぶなら、Sanrio English Masterがおすすめです。癇癪で悩むお子さまとコミュニケーションを取る時間を増やせるため、お子さまの考えや変化にも気づきやすいでしょう。
Sanrio English Masterでは、絵本やカードリーダー&カード、アルファベット積み木といった知育玩具やストーリー動画など、3歳児の興味を引くような教材を用意しています。教室へ通う習い事とは異なり、周囲を気にしなくてもよいため、お子さまを必要以上に叱る心配もありません。
また、メインキャラクターのエディも、イヤイヤ期で、最初は自分の意見を通そうとする場面もあります。しかし、様々な経験を経て、そのイヤイヤも収まっていきます。お子さまと共に成長していくパートナーなので、3歳のお子さまにもピッタリな内容です。
Sanrio English Masterでは、無料モニターキャンペーンを展開しています。申し込むと無料DVDセットがもらえるのもメリットのひとつです。
まとめ
3歳児の癇癪は、感情表現が未発達であることが原因で起こります。まずは癇癪が起こりにくい環境作りに配慮し、お子さまの気持ちを受け止めるように心がけましょう。なるべく心の余裕を持って対応できるように、おうちの方のコンディションを整えることも大切です。
お子さまと楽しみながら自宅で過ごすなら、Sanrio English Masterで遊びながら英語を学習するのがおすすめです。お子さまの興味・関心を引き出す、エンターテインメント性が高い教材をご用意しています。お子さまとの楽しい時間を設けたいと考えているおうちの方は、ぜひSanrio English Masterをご検討ください。